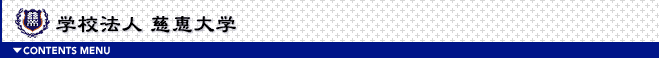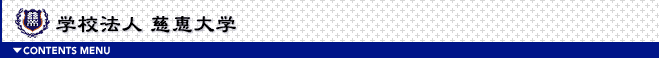|
|
| ���軰�±�������������罸���罸���� |
 |
 |
 ���������� ���������� |
|
 |
| ���ؿͲ� |
 |
|
|
 |
| ���ġ��� |
 |
|
|
 |
| ��� ���� |
 |
 |
 ���ꥭ����γ�ά ���ꥭ����γ�ά |
|
 |
| �����ؿͲʳز�ǧ�������5�ͤ��濴�Ȥʤ��Ƴ�ˤ����뻺���ؿͲʳز�θ���������ߤǤ��롣ǯ�֤�ʬ�ڤ���400���Ѥ���300��Ǥ��ꡢ�ä˴�μ�ѡ�������ˡ�ξ��㤬¿�������ؿͲʤθ�����2ǯ�ܤˤޤ�뤬��ɬ���ʤȤ���2������������ʤȤ���2���4���������Ǥ��롣���ʤ�����ؿͲʤϴ��֤���ڤ뤳�Ȥʤ�Ʊ���˸�������ǽ�Ǥ��ꡢ�ޤ�2����ǻ��ؿͲ����δ��ܤ�����ǽ�Ǥ��롣���θ��2���4����ˤ����Ƥ��ä����������ä�ʬ���ޤߡ��Х�ΤȤ줿�������Ǥ���褦�˥ץ�����ब�Ȥޤ�Ƥ��ꡢ���軺�ؿ�������֤��Ԥˤ������������Ǥʤ��Ԥˤ�ؿͲʤ����Ƥ������ºݤ����DZ��Ѳ�ǽ�ʥ��ꥭ����Ǥ��롣 |
 |
 |
������������ã��ɸ������2��������� |
|
 |
| 1.������ɸ�ʣǣɣϡ� |
 |
���������ɬ�פȤ���롢
| 1) |
������ͭ�Υץ饤�ޥꡦ���������롣 |
| 2) |
ǥ�����ؤʤ�Ӥ˿������ΰ��Ť�ɬ�פʴ���Ū�μ������롣 |
| 3) |
������ͭ�μ����ˤ��ߵް��Ť�и����롣 |
|
 |
2.��ư��ɸ�ʣӣ£ϡˡʷи���ɸ��
 |
| 1) |
���ʴط�
| (1) |
���Ρ��ۻ����ۻ���°ʪ�����������������δ��ܤ����롣 |
| (2) |
���ʤδ���Ū�ǻ�ˡ�������롣
 |
��ǵڤ�����ε��ܡ������ԤȤδ֤��ɤ����ߥ�˥����������ݤä���Ǥ�İ�褷���������������롣 |
 |
���ʤοǻ�����
���Ť�ɬ�פʴ���Ū���١���ǽ��ȤˤĤ��롣 |
|
| (3) |
���ʤθ���
���ʿ��Ť�ɬ�פʼ�θ�����»ܤ��뤤�ϰ��ꤷ�����η�̤�ɾ�����ơ����ԡ���²�ˤ狼��䤹���������뤳�Ȥ��Ǥ��롣
 |
ǥ�����������ȱֳ�Ūǥ��ȿ�� |
 |
Ķ���ȸ��� |
 |
ʬ�ڴƻ븡�� |
 |
�������ǡʹ���ñ��������������ףͣңɸ����� |
|
| (4) |
���ʤμ���ˡ�����ʬ�ڴ��������»ܤ��뤳�Ȥ��Ǥ��롣
 |
ǥ�����ؤ��Ф�����ʪ��ˡ������ǥ�����ؤ��Ф�����ʪ��ˡ�ˤĤ������»ܤǤ��롣 |
 |
ʬ�ڴ���ʬ�ڴ���ˡ�ˤĤ�����������ʬ�ڤδ�����и����롣 |
 |
���ʼ����ˡ����Ӽ��Ѵ����������ʼ��ˡ�����Ѵ��������������ˡ�ˤĤ������롣 |
|
| (5) |
���ʵߵ����ˤĤ��ơ�����Ŭ�ڤʥץ饤�ޥꡦ�������Ǥ��롣
 |
ǥ������νз졦ʢ�ˡʴޤࡢ�ҵܳ�ǥ���� |
 |
ǥ���桦����νз졦ʢ�� |
 |
����з� |
|
| (6) |
�������οǻ���Ԥ����۾����˥Ǥ��롣
 |
Apgar score |
 |
Silverman score |
 |
����¾�ο��ν긫 |
|
 |
| 2). |
�ؿͲʴط� |
| �� |
| (1) |
����������β�˶�����������롣 |
| (2) |
�����β������������ȼ���ۥ���Ķ����Ѳ������롣 |
| (3) |
�ؿͲʤδ���Ū�ǻ�ˡ�������롣
 |
��ǵڤ�����ε���
���ԤȤδ֤��ɤ����ߥ�˥����������ݤä���Ǥ�İ�褷���������������롣 |
 |
�ؿͲʤοǻ�
���Ť�ɬ�פʴ���Ū���١���ǽ��ȤˤĤ��롣 |
 |
�ؿͲʤθ���
�ؿͲʿ��Ť�ɬ�פʼ�θ�����»ܤ��뤤�ϰ��ꤷ�����η�̤�ɾ�����ơ����ԡ���²�ˤ狼��䤹���������뤳�Ȥ��Ǥ��롣 |
|
| (4) |
�ؿͲʼ����ˡ�ˤĤ��������и����롣
 |
�ؿͲ���������ʻҵ�����ɤ�ޤ�˼�ѤȤ��μ��Ѵ����������ؿͲ����������Ѥ���1�ޤ�����2����Ȥ��ƻ��ä������μ��Ѵ��������Ǥ��롣 |
 |
�ؿͲʰ��������ѤȤ��μ��Ѵ����������ؿͲʰ��������Ѥ���2����Ȥ��ƻ��ä������μ��Ѵ��������Ǥ��롣 |
|
| (5) |
�ؿͲ���ʪ��ˡ�ˤĤ������롣
 |
�ؿͲʴ����ɤ���ʪ��ˡ�����ؿͲʴ����ɤ���ʪ��ˡ�ˤĤ������»ܤǤ��롣 |
 |
�ؿͲ���������ʻҵ�����ɤ�ޤ�ˤ���ʬ����ˡ����
�ؿͲ������������ʬ����ˡ�ˤĤ������»ܤǤ��롣 |
 |
��ʬ��۾������㳲����ǽ���ҵܽз�ʤɡˤ���ʬ����ˡ�ˤĤ�������Ǥ��롣 |
|
| (6) |
�ؿͲʴ�ν������������Ǥ��롣
 |
���ܴ����������������Ԥα��ܴ������»ܤǤ��롣 |
 |
���˴��������������˴����ˤĤ������»ܤǤ��롣 |
|
| (7) |
�ؿͲʵߵޡʵ���ʢ�ɡˤˤĤ�������Ŭ�ڤʥץ饤�ޥꡦ�������Ǥ��롣
 |
����ʢ�ɤο��ǡ���
�����ε���ʢ�ɤ����Ū�˿��ǤǤ��롣 |
 |
�ؿͲʵߵ����μ����ˡ��
��Ѥ˽���Ȥ��ƻ��ä������Ѵ��������Ǥ��롣 |
|
| (8) |
��ǥ�ɤθ��������ŤˤĤ�������Ǥ��롣
 |
�����굻
�ҵ����¤�ơ��̿�ˡ���ա��ʡ��ƥ��ȡ����ո��� |
 |
����
��ǥ�ɤˤ���������Ͷȯˡ�����Ǥ��롣�������μ굻�����Ǥ��롣 |
|
|
|
|
 |
 |
 ��.��������ɸ(4������) ��.��������ɸ(4������) |
|
 |
| 1.. |
�и����٤��ǻ�ˡ���������굻 |
| �� |
| 1) |
����Ū���ؿͲʿ���ǽ��
| (1) |
��ǵڤ�����ε��� |
| �� |
���ԤȤδ֤��ɤ����ߥ�˥����������ݤä���Ǥ�Ԥ�������Ū��������Ū�� patient profile
��Ȥ館�뤳�Ȥ��Ǥ���褦�ˤʤ롣����ε��ܤϡ�������ָ������� (Problem Oriented Medical Record : POMR) ����褦�˹��פ��롣 |
| �� |
�� ����
�� ������
�� �����
�� �뺧��ǥ����ʬ����
�� ��²��
�� ������ |
| (2) |
���ؿͲʿǻ�ˡ |
| �� |
���ؿͲʿ��Ť�ɬ�פʴ���Ū���١���ǽ��ȤˤĤ��롣 |
| �� |
�� ��ǡʰ���Ū��Ǥ����紶��ǡ�
�� ���ǡʳ��ǡ��й�ǡ���ǡ�ǥ�ؤ� Leopold ����ˡ�ʤɡ�
�� 絡�ľIJ��
�� ���ɿǡ�Douglas �����ɡ�ʢ�����ɤ���¾��
�� �������οǻ���Apgar score, Silverman score ����¾�� |
 |
| 2) |
����Ū���ؿͲ������� |
| �� |
���ؿͲʿ��Ť�ɬ�פʼ�θ�����»ܤ��뤤�ϰ��ꤷ�����η�̤�ɾ�����ơ����ԡ���²�ˤ狼��䤹���������뤳�Ȥ�����롣ǥ�����ؤ˴ؤ��Ƥ϶ش��Ǥ��븡��ˡ��������˾�ޤ�������ˡ�����뤳�Ȥ�ʬ�����ʤ���Фʤ�ʤ���
| (1) |
�ؿͲ���ʬ�縡�� |
| �� |
�� �����β�ɽ�ο���
�� ����Ǵ�ո���
�� �ۥ�����٥ƥ���
���Ƽ�ۥ��� |
| (2) |
ǥ���ο��� |
| �� |
�� �ȱֳ�Ūǥ��ȿ��
�� Ķ���ȸ��� |
| (3) |
�����ɤθ��� |
| �� |
絥ȥꥳ��ʥ������ɸ���
絥��������ɸ���
����ߥ��������ɸ��� |
| (4) |
��˦�ǡ������ȿ����� |
| �� |
�� �ҵ������˦��
�� �ҵ������˦��
�� (�����ȿ�����)
�������Ϥ������μ�ˡ��ʻ���Ʒи����롣 |
| (5) |
�������� |
| �� |
�� ����ݥ����ԡ�
�� ʢ�ж�
�� (�ҵܶ�) |
| (6) |
Ķ���ȸ��� |
| �� |
�� �ɥץ顼ˡ
�� ����ˡ�ʷ��ŪĶ��������ˡ����ʢ��ŪĶ��������ˡ�� |
| (7) |
��������Ū���� |
| �� |
�� ����ñ��X������
�� ����¬�������̻��ơ�¦�̻��� : �ޥ���������������ޥ�ˡ��
�� �ҵ����¤��ˡ
�� ����X��CT����
�� ����MRI ����
�� (���¤��) |
 |
| 3) |
����Ū����ˡ |
| �� |
��ʪ�κ��ѡ������ѡ���ߺ��ѤˤĤ���������ʪ���šʹ�����������������ƥ�����������Ǯ����������ޤ�� ���Ǥ��롣
| (1) |
����䵤�ȯ�� |
| �� |
�� ���ޤ������������
�� ��Ϳ��ΰ����� |
| (2) |
���ͤλܹ� |
| �� |
�� ���⡢�鲼����������̮���濴��̮ |
| (3) |
�����Ѥ�ɾ���ʤ�Ӥ��б� |
| �� |
�� �Ŵ�����ˤĤ��Ƥ��μ� |
 |
|
| 2.. |
�и����٤��ɾ������֡����� |
| �� |
�����κ������Ū�ϡ����Ԥ��褹��ɾ��ȿ��ν긫����ñ�ʸ����긫�˴�Ť������̿��ǡ�������Ť�Ū�Τ˹Ԥ�ǽ�Ϥ�������뤳�Ȥˤ��롣
|
| �� |
| 1) |
���٤ι⤤�ɾ� |
| �� |
| (1) |
ʢ�� |
| (2) |
���� |
| (3) |
�����з� |
|
| �� |
���ؿͲ���ͭ�μ����˴�Ť�ʢ�ˡ����ˤ���¿��¸�ߤ���Τǡ����ؿͲʤθ����ˤ����Ƥ�������֤�����褦�ؤ�и����ʤ���Фʤ�ʤ��������ξɾ����褹�뻺�ؿͲʼ����ˤϰʲ��Τ褦�ʤ�Τ����롣�ҵܶڼ𡢻ҵ����ھɡ��ҵ�����ꡢ�ҵ�˵����ȿ��ꡢ�ҵ�α��ɡ��ҵ�αǿ�ɡ���к���ɡ��ҵ���°��ꡢ���α��ɡ����αǿ�ɡ�����ҵ�����ɡ�������ɷ�ɸ����������ˡ�����ʢ��ꡢ���ҵ�����ɤ����ꡢ�����ǥ���˴�Ϣ�����ΤȤ��ƻҵܳ�ǥ��������ή�Ỻ���������ס�������������Υ�������ҵ����������ˤʤɤ��Τ��Ƥ��롣 |
| 2) |
�۵ޤ��פ���ɾ������� |
| �� |
| (1) |
����ʢ�� |
| �� |
����������и������ʤ��������Ť˻��ä��뤳�ȡ� |
| �� |
���ؿͲʼ����ˤ�����ʢ�ɤμ���Ϥ�����¿����������ͭ�μ����ˤ�����ʢ�ɤ�ߵް��ŤȤ��Ƹ������뤳�Ȥ�ɬ�ܤǤ��ꡢ���ؿͲʤθ����ˤ����Ƥ�������֤�Ū�Τ˴��̤�������Ť�Ԥ���ǽ�Ϥ�������ʤ���Фʤ�ʤ�������ʢ�ɤ��褹�뻺�ؿͲʴ�Ϣ�����ˤϻҵܳ�ǥ������������DZž������з�ʤɤ����롣 |
| (2) |
ή���Ỻ����������� |
|
| 3) |
�и�����������������֡����ʤ���Фʤ�ʤ�����Ū�μ���ޤ�� |
| �� |
| (1) |
���ʴط� |
| �� |
�� ǥ����ʬ�ڡ�����ʤ�Ӥ˿�����������������
�� ǥ���θ���������
�� ����ǥ�ؤγ������
�� ����ʬ���裱���ʤ�Ӥ��裲���δ���
�� ����Ƭ��ʬ�ڤˤ���������ڽ�����δ�����ľ�ܲ��
�� ���ﻺ��δ���
�� ����������
�� ʢ���벦�ڳ��Ѥηи�
�� ή���Ỻ�δ���
�� ���ʽз���Ф��������ˡ������ |
| (2) |
�ؿͲʴط� |
| �� |
�� ������β�˶������
�� �뾲�����������Ρ�����Ϥ���ʬ��Ĵ��Ϥ�����
�� �ؿͲ���������ο��Ǥʤ�Ӥ˼��ŷײ��Ω��
�� �ؿͲ���������μ�Ѥؤ���1����Ȥ��Ƥλ���
�� �ؿͲʰ���������������ˡ������
�� �ؿͲʰ�������μ�Ѥؤ�2����Ȥ��Ƥλ��äηи�
�� �ؿͲʰ�������ν���Ū���Ť�����
�� ��ǥ�ɡ���ʬ��������Ԥγ���ˤ����븡��
�� �ؿͲ����ﴶ���ɤθ��������� |
|
|
|
 |
 |
 ��.��������ɸ(4������) ��.��������ɸ(4������) |
|
 |
| 1. |
������ɸ�ʣǣɣϡ� |
| �� |
���������ɬ�פȤ���롢
| 1) |
������ͭ�Υץ饤�ޥꡦ���������롣 |
| 2) |
ǥ�����ؤʤ�Ӥ˿������ΰ��Ť�ɬ�פʴ���Ū�μ������롣 |
| 3) |
������ͭ�μ����ˤ��ߵް��Ť�и����롣 |
 |
|
| 2. |
��ư��ɸ�ʣӣ£ϡˡʷи���ɸ�� |
| �� |
| 1) |
���ʴط�
| (1) |
���Ρ��ۻ����ۻ���°ʪ�����������������δ��ܤ����롣 |
| (2) |
���ʤδ���Ū�ǻ�ˡ�������롣 |
| �� |
 |
�ǵڤ�����ε��ܡ���
���ԤȤδ֤��ɤ����ߥ�˥����������ݤä���Ǥ�İ�褷���������������롣 |
 |
���ʤοǻ�����
���Ť�ɬ�פʴ���Ū���١���ǽ��ȤˤĤ��롣 |
 |
���ʤθ�������
���ʿ��Ť�ɬ�פʼ�θ�����»ܤ��뤤�ϰ��ꤷ�����η�̤�ɾ�����ơ����ԡ���²�ˤ狼��䤹���������뤳�Ȥ��Ǥ��롣
[1]ǥ�����������ȱֳ�Ūǥ��ȿ��
[2]Ķ���ȸ���
[3]ʬ�ڴƻ븡��
[4]�������ǡʹ���ñ��������������ףͣңɸ�����
[5]���������ǡ��ӿ帡���� |
 |
���ʤμ���ˡ�����ʬ�ڴ��������»ܤ��뤳�Ȥ��Ǥ��롣
| [1] |
ǥ�����ؤ��Ф�����ʪ��ˡ����
ǥ�����ؤ��Ф�����ʪ��ˡ�ˤĤ������»ܤǤ��롣 |
| [2] |
ʬ�ڴ�������
ʬ�ڴ���ˡ�ˤĤ�����������ʬ�ڤ�ľ�ܴ�����и����롣ʬ�ڿʹԤˤ�����۾���������Ǥ��롣 |
| [3] |
���ʼ����ˡ����Ӽ��Ѵ��������������ʼ��ˡ�����Ѵ��������������ˡ�ˤĤ������� |
|
 |
���ʵߵ����ˤĤ��ơ�����Ŭ�ڤʥץ饤�ޥꡦ�������Ǥ��롣
[1]ǥ������νз졦ʢ�ˡʴޤࡢ�ҵܳ�ǥ����
[2]ǥ���桦����νз졦ʢ��
[3]����з� |
 |
��ʻ��ǥ���Ȥ��δ�����ˡ�ˤĤ������롣
[1]��Ǣ�¹�ʻǥ��
[2]��������ʻǥ��
[3]����¾�ι�ʻǥ�� |
 |
�������οǻ���Ԥ����۾����˥Ǥ��롣
[1]Apgar score
[2]Silverman score
[3]����¾�ο��ν긫 |
 |
|
| 2) |
�ؿͲʴط�
| (1) |
����������β�˶�����������롣 |
| (2) |
�����β������������ȼ���ۥ���Ķ����Ѳ������롣 |
| (3) |
�ؿͲʤδ���Ū�ǻ�ˡ�������롣 |
| �� |
 |
��ǵڤ�����ε��ܡ�����
���ԤȤδ֤��ɤ����ߥ�˥����������ݤä���Ǥ�İ�褷���������������롣 |
 |
�ؿͲʤοǻ�������
���Ť�ɬ�פʴ���Ū���١���ǽ��ȤˤĤ��롣 |
 |
�ؿͲʤθ���������
�ؿͲʿ��Ť�ɬ�פʼ�θ�����»ܤ��뤤�ϰ��ꤷ�������η�̤�ɾ�����ơ����ԡ���²�ˤ狼��䤹���������뤳�Ȥ��Ǥ��롣 |
 |
| (4) |
�ؿͲʼ����ˡ�ˤĤ��������и����롣
 |
�ؿͲ���������ʻҵ�����ɤ�ޤ�˼�ѤȤ��μ��Ѵ�����������
�ؿͲ��� �������Ѥؽ���Ȥ��ƻ��ä������μ��Ѵ��������Ǥ��롣 |
 |
�ؿͲʰ��������ѤȤ��μ��Ѵ�����������
�ؿͲʰ��������Ѥؽ���Ȥ��ƻ��ä������μ��Ѵ��������Ǥ��롣 |
|
| (5) |
�ؿͲ���ʪ��ˡ�ˤĤ������롣
 |
�ؿͲʴ����ɤ���ʪ��ˡ������
�ؿͲʴ����ɤ���ʪ��ˡ�ˤĤ������»ܤǤ��롣 |
 |
�ؿͲ���������ʻҵ�����ɤ�ޤ�ˤ���ʬ����ˡ������
�ؿͲ������������ʬ����ˡ�ˤĤ������»ܤǤ��롣 |
 |
��ʬ��۾������㳲����ǽ���ҵܽз�ʤɡˤ���ʬ����ˡ�ˤĤ�������Ǥ��롣 |
 |
��ǯ���㳲�ʤɤؤΥۥ����佼��ˡ�ˤĤ�������Ǥ��롣 |
 |
�ؿͲʰ�������β�����ˡ������
�ؿͲʰ�������β�����ˡ�ˤĤ������������������к����Ǥ��롣 |
|
| (6) |
�ؿͲʴ�ν������������Ǥ��롣
 |
���ܴ���������
���������Ԥα��ܴ������»ܤǤ��롣 |
 |
���˴����������������˴����ˤĤ������»ܤǤ��롣 |
|
| (7) |
�ؿͲʵߵޡʵ���ʢ�ɡˤˤĤ�������Ŭ�ڤʥץ饤�ޥꡦ�������Ǥ��롣
 |
����ʢ�ɤο���
�����ε���ʢ�ɤ����Ū�˿��ǤǤ��롣 |
 |
�ؿͲʵߵ����μ����ˡ����
��Ѥ˽���Ȥ��ƻ��ä������Ѵ��������Ǥ��롣 |
|
| (8) |
��ǥ�ɤθ��������ŤˤĤ�������Ǥ��롣 |
|
|
|
 |
 |
 ��֥������塼�� ��֥������塼�� |
|
 |
| 1) |
�������֤��̤��ƻ�������ؿͲ�������ؿͲʳ�����������塼��˹�碌�Ƹ��������롣 |
| 2) |
��Ǥ���(���ܻ��ؿͲʳز�ǧ�껺�ؿͲ������)�ʤ�Ӥ˼�̳ô����դ줾��θ�����ˤĤ����������ο��Ťʤ�Ӥ˼�Ѽ��Ǥθ������Ƴ���롣 |
|
|
 |
 |
 ���֥������塼���ͽ��� ���֥������塼���ͽ��� |
|
 |
| �� |
��
|
�� |
�� |
�� |
�� |
�� |
| 8:30 |
����ͽ�ꥫ��ե����
|
�� |
�� |
�� |
��Ѿ��㥫��ե���� |
�� |
| 9:00 |
�ؿͲ�

���� |
��� |
���ʳ��� |
�����ؿͲ����� |
��� |
�����ؿͲ�
���� |
| 12:00 |
��٤�
|
��٤� |
��٤� |
��٤� |
��٤� |
��٤� |
| 13:00 |
�����ؿͲ�

����

��ǯ������ |
���
|
�����ؿͲ�

����

��ǯ������ |
�����ؿ�

����

���糰��
|
��� |
�����ؿͲ�
���� |
| 15:00 |
�������㥫��ե����
|
�� |
�������㥫��ե����
|
| 16:00 |
���衦����Ǹ����ȤΥ���ե����*
|
����������ե����*
|
(CPC)
|
| 17:00 |
���ɲ�

����ȯɽ��*
|
�� |
�� |
|
| �� |
��§�Ȥ������1�� |
| �� |
1)ʬ�ڡ��۵�ѡ��ߵ��Լ��ŤˤϿ��Ω����
2)����ľ��1��ʾ�Ԥ���
3)�ز�����ˤϸ����ΰ�ĤȤ���ȯɽ�ޤ��ϻ��ä����롣(4����)
|
|