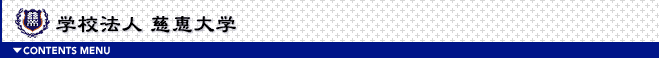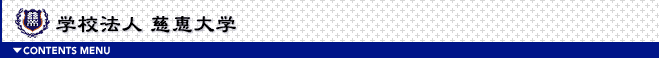| (1年目) |
| |
(1) |
病歴採取を含めた問診(現病歴、既往歴、社会的背景など)、初期診察(全身的所見、神経学的所見など)を正しく行い、正確なカルテ記載ができる。 |
| |
(2) |
患者のもつ障害を、機能障害、能力障害、社会的不利それぞれのレベルで明らかにすることができる。 |
| |
(3) |
障害に対するアプローチを考察し、指導医の監督下で的確なリハ処方を行うことができる。 |
| |
(4) |
指導医の監督下で患者およびその家族に適切な病状説明を行うことができる。 |
| |
(5) |
患者情報を共有するために理学療法士、作業療法士、言語療法士と密接なコミュニケーションをとることができる。 |
| |
(6) |
慢性期合併症(肺炎、尿路感染症、瘡創など)の発症を見落とすことなく指摘することができる。そして、それに対する的確な治療方針を指導医とともに決定することができる。 |
| |
(7) |
初期臨床研修で得た全身管理(呼吸循環管理、点滴処方、バイタル・サイン・チェックなど)、救急対処(心臓マッサージ、気管内挿管、中心静脈確保など)の知識・技術をさらに高める。 |
| |
(8) |
リハ科医師として必要な検査手技(筋電図検査、嚥下造影検査、髄液検査など)を、指導医とともに行えるようになる。 |
| |
(9) |
神経放射線学的検査(頭部CT、頭部MRI/MRA、頸椎単純撮影など)を指導医の監督下で読影・解釈することができる。 |
| |
(10) |
リハビリテーション・チームの仕組み、チームを構成するリハ医療関連職(療法士、ソーシャルワーカー、義肢装具士など)の業務内容を理解する。 |
| |
(11) |
リハビリテーション・カンファレンスに参加し、その進め方を学ぶ。 |
| |
(12) |
義肢・装具に関する基本的知識を習得する。 |
| |
(13) |
リサーチ・カンファレンスで英文文献を紹介し、リハ医学研究の動向を学ぶ。 |
| |
(14) |
障害者の心理状態を理解し、障害者に接する態度を学ぶ。 |
 |
| (2年目) |
| |
(1) |
自立して患者の評価および患者に対するリハ処方を行えるようになる。 |
| |
(2) |
入院のみならず、リハ科外来診療に必要な知識・技術を習得する。また、患者および患者の家族に自宅での生活指導を行えるようになる。 |
| |
(3) |
合併症発症時に、自らの判断で処置を行えるようになる。他科へのコンサルトも適切に行える。 |
| |
(4) |
リハ科における基本的検査を自立して行い、その結果を解釈できるようになる。 |
| |
(5) |
神経放射線学的検査を自立して読影できるようになる。また、その結果を的確に患者、患者家族、リハ医療関連職に説明することができる。 |
| |
(6) |
リハビリテーション・カンファレンスに、積極的に参加する。 |
| |
(7) |
義肢・装具を指導医の監督下で処方できる。 |
| |
(8) |
各種研究プロジェクトに参加、指導医の研究を手伝いながら、将来の研究テーマを決定する。 |
| |
(9) |
リサーチ・カンファレンスで自らが興味をもったリハ医学の研究を紹介する。 |
| |
(10) |
日本リハ医学会学術集会に参加、現在におけるリハ医学臨床面および研究面の動向を学ぶ。 |
| |
(11) |
日本リハ医学会地方会で、症例報告を行う。 |
 |
| (3年目) |
| |
(1) |
1年目および2年目に習得したリハ科診療に必要な知識・技術をさらに高める。 |
| |
(2) |
リハビリテーション・チームのリーダーとして、療法士などのリハ医療関連職スタッフに指示・指導を行う。 |
| |
(3) |
リハビリテーション・カンファレンスにおいて司会進行役を担当し、カンファレンスの結果をまとめ、患者の治療方針を参加者に納得させることができる。 |
| |
(4) |
医学生、看護学生の率前教育に参加する。 |
| |
(5) |
リハ科特殊外来を上級医の監督下で担当し、より専門的な知識を身につける。 |
| |
(6) |
自らが主研究者となり、臨床もしくは基礎研究の研究計画をたてる。そして、上級医の指導のもと研究を進め、国内外の学会で発表できるようになる。 |
| |
(7) |
研究結果を邦文もしくは英文の論文としてまとめあげ、主要医学雑誌に投稿する。 |
| |
(8) |
リハ科医師として、いかなる疾病をもった患者に対しても、全人的に接することができるようになる。 |
| |
(9) |
リハ科専門医試験受験の準備、学位申請の準備をする。 |
|
尚、3年間のレジデント期間中には、原則として以下の各疾患の診療に満遍なくあたることができるように配慮し、患者の割り当てを行うこととしている。 |
| |
(1) |
脳神経疾患(脳卒中、頭部外傷、脳腫瘍など) |
| |
(2) |
脊髄疾患(脊髄損傷、脊髄炎など) |
| |
(3) |
神経筋疾患(パーキンソン病、脊髄小脳変性症、ギラン・バレー症候群など) |
| |
(4) |
骨関節疾患(関節リウマチ、変形性関節症など) |
| |
(5) |
小児疾患(筋ジストロフィー、脳性麻痺、二分脊椎など) |
| |
(6) |
切断(大腿切断、下腿切断、上肢切断など) |
| |
(7) |
呼吸器・循環器疾患(慢性閉塞性肺疾患、心筋梗塞など) |
| |
(8) |
その他(リンパ浮腫、廃用性筋萎縮など) |
 |