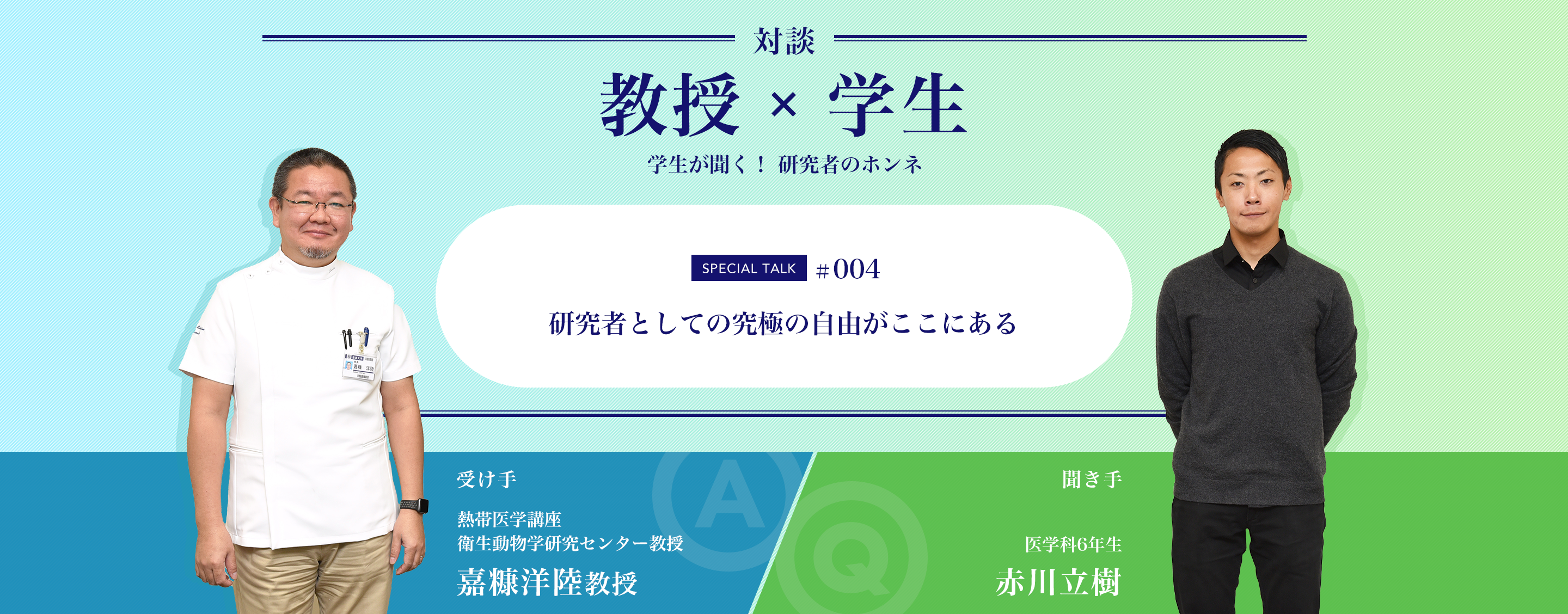


私立大学研究ブランディング事業「働く人の疲労とストレスに対するレジリエンスを強化するEvidence-based Methodsの開発」は、「病気を診ずして 病人を診よ」という建学の精神をブランド化するものとして位置付けられています。今回は寄生虫・細菌・ウイルス等による感染症に潜む、多様な生命現象のメカニズムについての基礎・応用研究に取り組む、熱帯学医学講座の担当教授である嘉糠洋陸さんに、本学における研究の意義について話を伺いました。
自由に研究するために活動の場を変えてきた
赤川
―先生は慈恵の出身ではないとお聞きしています。どうして慈恵にいらしたのでしょうか。
嘉糠
私は医師ではありません。出身は東京大学の農学部獣医学科で、最初に教員になったのが、東京大学の薬学部でした。
東京大学自体は素晴らしい大学だと思いますが、正直、私は研究のやりにくさを感じていました。「主流派はかくあるべき」のような目に見えない縛りを覚え、私の目指す研究を好きに進められる雰囲気ではありませんでした。

私は米国留学時から今に至るまで、一貫して「蚊やマダニなどの節足動物が、どのように病原体を媒介するのか」を研究してきました。東京大学でその研究をしようとしても、「危険な研究は困る」、「それよりもっと大事なことがあるのでは」といった様々なプレッシャーが伝わってきて、研究がやりづらかったんですね。
そんな時に、北海道の国立単科大学である帯広畜産大学から声がかかりました。原虫病研究センターの新設分野の教授になりませんかと。そこなら自由に自分の研究ができると思って引き受けました。2005年12月のことです。当初は助教授(当時)ポジションだと思っていたら、蓋を開けたら教授でした。32歳の時のことです。
帯広畜産大学では、感染症のセンターということもあって、自由に研究に取り組めました。今でも私の研究室の土台になっている重要な知見の幾つかを、ここで得ることが出来ました。ただ、研究には限界がありました。研究対象が動物に限定されていて、ヒトの感染症の研究は大っぴらにはできません。帯広で始めたマラリアの研究も随分と面白くなってきて、そんな時に本学が熱帯医学講座の教授を募集していることを知り、手を挙げました。

赤川
―本学のことはご存知だったのでしょうか。また、どんな印象を持たれていたのでしょうか。
嘉糠
高校生の時から、変わった大学だと思って見ていました。当時、国立大学の試験日(前期日程)、と慈恵の試験日が同じ日だったのです。つまり、慈恵を受ける学生は、国立の医学部の併願は不可能だったのです。現在の慈恵はまさに“首都圏の大学”で、地方に行くと知名度は高くはないですが、当時はそんな「フシギな大学」として、名前を知っている受験生も多かったはずです(笑)。
嘉糠
東京大学を卒業してから、大阪大学の大学院医学系研究科の博士課程に進学しました。現在は慶應義塾大学医学部で教授をされてる岡野栄之先生の研究室の門を叩きました。その岡野研の3つ上に、今は本学解剖学の教授になっている岡部正隆先生がいました。医学部を卒業しているのに、歴とした医師なのに、岡部先生は東京を離れて関西にやってきて、無脊椎動物の神経発生の研究をしていました。兄弟子の岡部先生からはいろいろと研究の手ほどきを受けましたが、「慈恵の人は自由なんだ」と感じました。本学の印象として、これはかなりのインパクトがありましたね。ちなみに、岡部先生、カラオケでアニソンを歌わせると当時から天下一品でね(笑)。

教授選の時に改めて慈恵のことを調べましたが、知れば知るほど面白い大学だと。学祖である高木兼寛についての本や文献をそぞろ読んだのですが、立ち位置が一線を画していて、他の人とは研究マインドが明確に違うのです。固定観念に縛られずに自由に振る舞う、それが自分に合っていると思いました。
実際に教授に選ばれた時、当時の栗原学長(現・理事長)から「教育と大学運営をしっかりやってもらえれば、それで給料分です。他の時間は何をしても自由です。ですから、いい研究をしてください」と言われて、「これがこの大学の風土なんだ」と鳥肌が立ちましたね。

固定観念に縛られず、自由に振る舞う研究マインドに鳥肌が立ちました。
他大学とは違うウエット&スティッキーさ

赤川
―本学の特徴はどんなところにあると思われますか。
嘉糠
私はウェット&スティッキーだと言っています。
赤川
―スティッキーというと「べたつく」とかそういう意味ですよね。
嘉糠
そうです。まず決してドライではない。分かりやすい例を挙げますね。臨床実習で、定例のカンファレンスではない自主的な勉強会を指導医や先輩にお願いすると、嫌がらずにやってくれます。これがウェットです。そして、その後に必ず皆でご飯を食べに行く。これがスティッキーです。
今時こんなことをやっている医学部、昭和ですかと笑われそうですよね(笑)。密度が濃いのです。あまり知られていませんが、4附属病院合計で3000床を誇る本学は、学生と教職員の比率が1対1です。これは、ある世界大学ランキングで日本医科大学と並んで第一位なんです。他者から見たら賛否両論あるのだと思いますが、このウェット&スティッキーが、本学の研究や診療を支えているひとつの柱だと考えています。慈恵に縁もゆかりもない私だからこそ、分かることです。

確かにみなさん仲が良いですね。
嘉糠
教授選考の質疑応答の時、最初の質問が「あなたは、お酒は好きですか」で、度肝を抜かれました。「こんな時になぜ?」と思いましたが、スティッキーなコミュニケーションを厭わない人かどうか、品定めされていたのかも知れませんね。果たして、着任してから1カ月間はほぼ毎日飲み会でした。私自身は来て良かったと思いましたが(笑)。

ドライでないところが他大学との大きな違いです。

赤川
―私も入学して良かったと思っています。私は7浪相当なんです。大学を出て芸術系に進もうと海外に留学してから、医学を学ぼうと考えを変えて、勉強し直して2年目に合格しました。そういう私でも受け入れてくれた大学です。
嘉糠
そういえば、あなたは、沖縄で意気投合した漁師の人のところに居候してみたりの経験などもありますよね(笑)。本学は、現役か浪人かどうかは関係なく、その人の能力や適性をみて受け入れています。特筆すべきは、学生ごとの個性、つまり集団の多様性を大切にしている大学だということです。実際にはウェット&スティッキーが苦手な学生もいます。それも受け入れているんですね。一度慈恵に入れば、全員が仲間なのです。
卒業後の進路も多種多様です。医師になる人ばかりではなく、官僚になる人、国際機関で働いている人、変わったところでは、小説家になっている人もいます。
赤川
―ミュージシャンになった人もいますね。
嘉糠
卒後の行き先はバリエーションに富んでいます。けれど、ここはずっと変わらない、彼らのホームグラウンドなんです。いつでも帰ってくることができる。「慈恵」というブランドに、ずっとロイヤリティを持ち続けることができます。良い意味での「秘密結社」なんです。また昭和風なキーワードで申し訳ないですが(笑)。
赤川
―入学式でも学長が「君たちは慈恵の宝だ」と仰っていますが、大切にされているんだな、と日々感じています。
嘉糠
その宝物であるあなた達を育てる医学教育にも、慈恵らしさが表れています。国際基準に対応した医学教育として、見学型臨床実習、そしてその後の診療参加型臨床実習が求められています。つまり、まずはポリクリで診療科をぐるっと一周目、次いで、スチューデント・ドクターとして診療業務を参加しながら二周目をする。それを“ガチでやっている”のは、本学くらいです。他の大学では、時間を割けるマンパワーや臨床を行う病院の不足等の問題があって、狙い通りのものになっていないのが現状です。多くの長所に加え、ウェット&スティッキーの本学だからこそ可能なのです。まともに考えると大変なことでも、当たり前のこととしてやってしまっています。
創設者の精神が自由な研究につながっている
赤川
―本学で研究していてどんなことができたのでしょうか。
嘉糠
例えば、寄生虫卵内服療法の研究ですね。ブタの寄生虫をヒトに人為的に感染させることで、免疫応答を調節し、自己免疫疾患やアレルギー疾患の治療に役立てようというものです。その研究を進めるには、寄生虫卵を被験者に飲ませることが必要です。日本どころか、アジアですら臨床研究の実施例がありません。さすがの私も、許されるのか半信半疑で、本学の倫理委員会にこの研究を申請しました。ヒアリングに呼ばれ、恐る恐る出頭したら、許可が下りただけでなく、積極的に進めるように激励されました。
他の大学であれば、あれこれ理由をつけて止められるでしょう。本学では、究極の自由な環境の中で研究ができる。大学に漂う空気が違うのです。実際にユニークな研究があちらこちらで行われています。

なぜそれほど他の大学と違うのでしょうか。
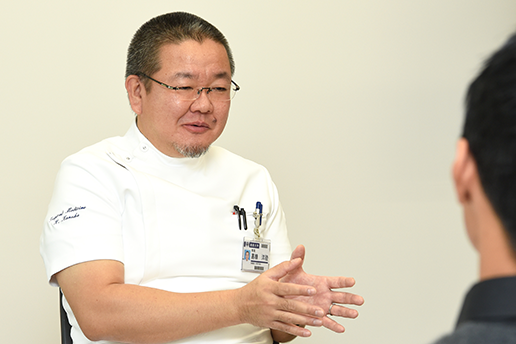
赤川
―確かに興味深い研究を行なっている先生が多いとは思いますが、なぜそれほど他の大学と違うのでしょうか。
嘉糠
慈恵と言えば臨床であって、いい意味で社会から研究に期待されていないからだと思います。東京大学や京都大学、私学で言えば慶應義塾大学のような知名度の高い大学は、国民の負託も大きく、期せずともメインストリームを追うことになります。
しかし、本学は研究の面ではそれほど認知度も高くありません。期待してくれているのは、慈恵が好きな、ファンと言ってもいい一部の人たちです。だから何にも縛られずに、自由に研究できます。主流でなくても良いんです。でも大事なことは沢山あります。そこを研究するのが私たちの使命だとも思っています。
例えば、iPS細胞を使った基礎・応用研究にしても、本学の研究者は他大学とは違うアプローチを好みます。我が道を行く、です。iPS細胞研究の全体としてのトレンドはもちろん重要です。しかし、そこに追随しなくても良いのではないかと考えるのが私達です。それが許される大学なんですね。おかげで、私も好き勝手に研究をやらせてもらっています(笑)。
赤川
―確かに知名度が低いかも知れませんが、能力の高い人が多いと感じています。でも、そういう風土はなぜ生まれたのでしょうか。
嘉糠
先ほども学祖である高木兼寛の研究姿勢に触れましたが、1世紀以上経った今でも、それが綿々と引き継がれていると思っています。高木は脚気の研究で名を成した人です。脚気は細菌が原因だと世の中が右へ倣えで言っている時に、鋭い疫学的考察から栄養説を唱えて、海軍軍医としての立場から軍艦を使って大胆な実験を行なっています。
この実験は壮大なスケールです。実際に「筑波」という軍艦を実験航海させ、脚気患者がたくさん出た「龍驤」と同じ航路を辿らせます。約9カ月間の、太平洋ルートです。その際、白米ではなく麦飯を使った食事を与えることで、脚気の原因が食事にあることを証明しようとしました。失敗すれば、切腹する覚悟だったと言われています。結果は見事、高木の目論見通りでした。

でも、慎重なところも知られています。高木は、この実験航海中に、同時に犬を使った脚気の実験も行なっています。その結果、犬に対しても脚気の症状を起こすことに成功したのですが、あくまで「脚気のような症状が出た」に留め、断定はしていない。功績に走って、焦るようなことはしないのです。
高木の研究姿勢は、130余年後の本学で今もなお、「研究に自由に取り組む」、「他人の研究を邪魔しない」、「研究を足し算で考える」などとして表されているのだと感じています。

そのDNAが130年経っても変わっていないということは凄いと思います。
嘉糠
単科医科大学として、他と同化するのではなく、違うものを求めてきたからでしょうね。ただ、研究において自由であることは、時として大変なことでもあります。
私は研究について本学の研究者から個別に相談を受けることがよくあります。その際、「それは先生がやらなくても良いのでは」と指摘させていただくことが多々あります。研究はつい続けてしまいがちですが、研究のための研究はやらなくても良いと思うのです。学祖高木兼寛は、そんな研究は決してやらなかったでしょう。
研究者には研究を止める自由もあります。やりたいものができたら、その時に突き進めばいいのです。それが出来るのが、慈恵なのです。
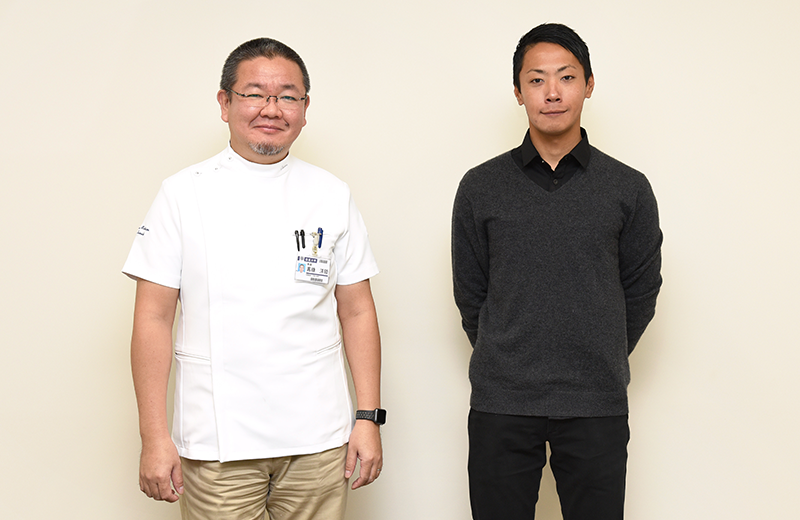
対談者プロフィール

熱帯医学講座
衛生動物学研究センター 教授
嘉糠洋陸(かぬか ひろたか)
山梨県に生まれる。高校1年時の生物の授業で、DNAを中心としたセントラルドグマを知る。すぐさま本屋に自転車を走らせ「遺伝子が語る生命像」(本庶佑著)を買い求め、既に遺伝子を“切った貼った”することが可能な時代であることを知り、一切の迷い無く科学者の道を志す。東京大学農学部獣医学科卒業、大阪大学大学院医学研究科博士課程修了、博士(医学)。2005年より帯広畜産大学原虫病研究センター教授、2011年より東京慈恵会医科大学熱帯医学講座教授。衛生動物学研究センター長兼務。座右の銘は「好きこそものの上手なれ」。

医学科6年生
赤川立樹(あかがわ たつき)
那須高原海城高校卒業後、興味を追い求めふらふらと生きていたが、多様性と独創性を重んじる東京慈恵会医科大学に25歳で入学。現在は医学に邁進する傍ら、サーフィンのインストラクター・日焼け止めベンチャー企業のアドバイザーなどとしても活動する。大学ではヨット部・Jazz研・自動車部に所属。座右の書はギヨーム・アポリネール著『Calligrammes』。

