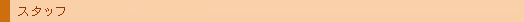 |
|
 |
 |
ウイルス研究の醍醐味の一つに、ウイルスと感染宿主との関係を研究することで、生命機能そのものを明らかにすることが挙げられます。がん遺伝子が、レトロウイルスの研究から発見されたのが良い例です。我々は「疲れたらヘルペスが出る」という現象をきっかけとして、「疲労」という生命現象そのものを明らかにしようとしています。我々が主に扱っているヒトヘルペスウイルス6(HHV-6)とHHV-7は、疲労の刺激で潜伏感染から再活性化する性質を持ちます。我々は、この性質を利用して、唾液中へ再活性化するHHV-6、HHV-7を利用して客観的に疲労を測定する方法を開発しました。また、宿主の疲労のシグナル伝達径路を同定し、疲労因子や疲労回復因子を同定しました。現在、疲労研究は産学共同の体制で、診断キットの開発や、予防薬の開発研究も行なっています。
同時にこの様な視点での研究は、これまで原因が不明であった難病などの疾患の原因究明につながります。なぜなら、この様な疾患は、遺伝子変異などの宿主の要因を、持続・潜伏感染しているウイルスが修飾して疾患を形成している可能性があるからです。特に精神疾患では、効果量(effect size)の大 きい遺伝子変異が発見されておらず、大規模遺伝子研究による原因究明は手詰まり状態でした。我々は、脳内に潜伏感染するHHV-6の遺伝子発現を研究し、うつ病などの気分障害を引き起こすHHV-6潜伏感染遺伝子SITH-1を発見しました。その後の研究で、SITH-1は、うつ病などの気分障害患者の6割以上で発現が確認され、動物実験によっても、うつ病発症の原因となることが判ってきました。今後は、これらの研究を押し進め、「疲労」と「うつ病」の関係の解明や、これらの治療法・予防法の開発を行ないたいと考えています。 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
臨床研究、基礎研究を自ら展開することが可能な、分子生物学的知識と研究手法を身につける。 |
 |
生命機能研究や疾患研究に応用可能な 、ウイルス学的知識と手法を身につける。 |
 |
臨床医学的応用や疾患治療につながる、基礎医学的研究能力、発明・発見能力を養う。 |
 |
研究結果をまとめて、英語での論文作製、学会発表ができる。 |
|
| |

