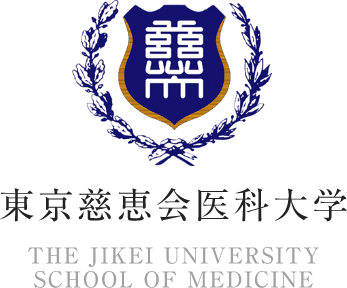第20回 危険な状態だった患者さんが元気に歩いて帰る姿を見れることが嬉しい
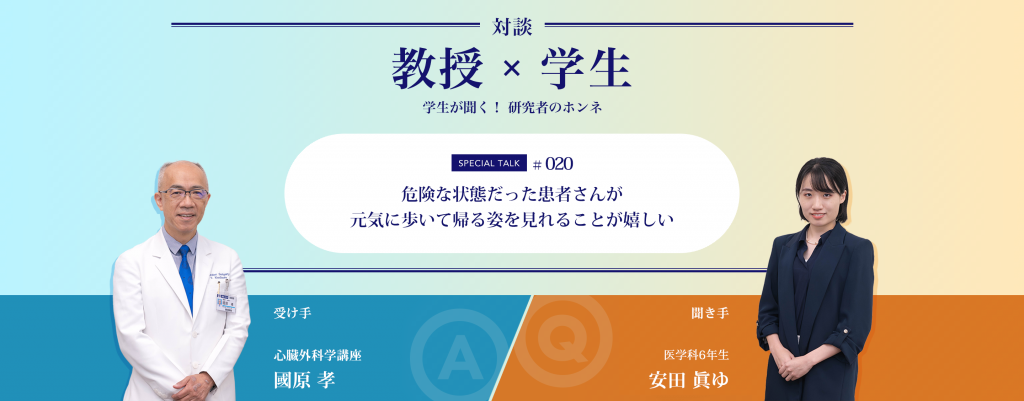
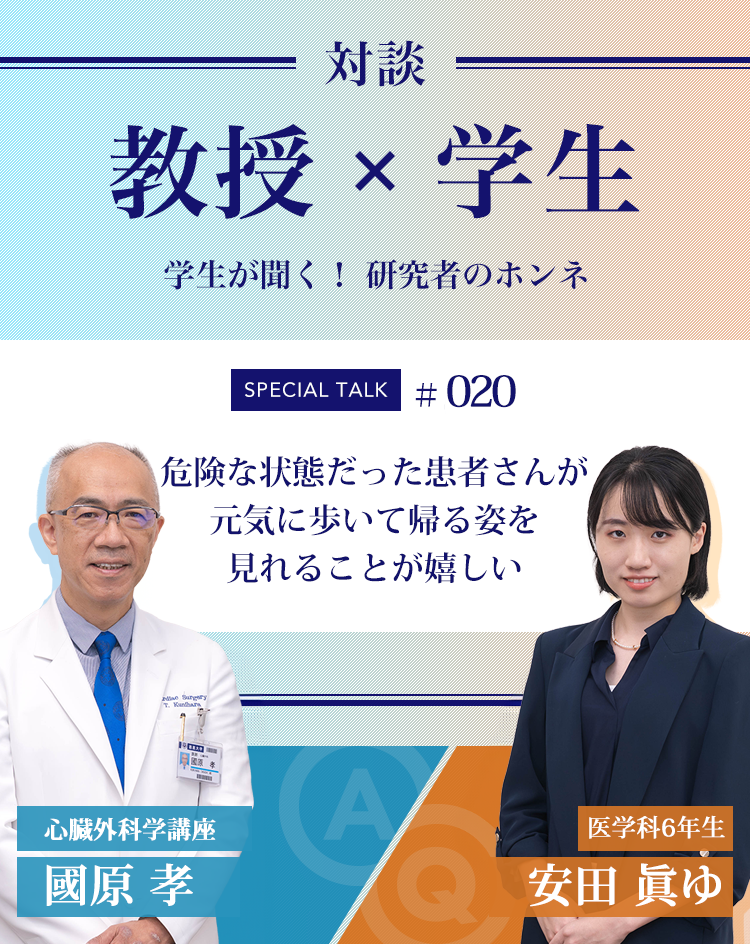

今回ご紹介するのは、心臓外科学講座担当教授の國原孝さんです。様々な心臓外科手術に精通し、特に人工弁を使用せずに大動脈の弁を修復する「大動脈弁形成術」の日本の第一人者です。
中学校の警備員さんから背中を押されて医師に


安田
医師を志すきっかけはなんだったのでしょうか。
國原
もともとアフリカの飢饉が問題になっていた頃に、そうした困っている人を助ける仕事がしたいと、北海道大学の農学部に行こうと考えていました。そんな時に中学校の時の警備員の方に「農学部よりも医者になった方がすぐに人を助けられるよ」と言われたんです。しかも「浪人するお金がないなら援助してあげる」とまで。
まさに現代版足長おじさんのような方で、中学校のOBを集めて警備員室をコミュニケーションの場にして人助けをしていたんです。今でも年に1、2回は集まって食事をしたりしています。結局浪人した私はその方に予備校のお金を出してもらって医学部に進学することができました。
外科医になろうと考えたのは、外科が最後の砦だからです。内科医が治療を施して、それでも治せない病気もあって、外科医にバトンタッチします。最後の砦として最後まで治療するというところに魅力を感じました。当時の北大の第二外科は心臓や血管、肺も担当していて、血管を扱える外科医になろうと第二外科を選びました。
卒業後は3年間大学外の病院にローテーションするのですが、当時結婚したばかりで札幌にいたいと考えて、忙しくてみんなが敬遠していた心臓がメインの国立札幌病院に勤務しました。泊まりがけの勤務が毎日続いて、新婚なのに1ヶ月も家に帰れないような状態でした。しかし、そこで心臓外科の魅力を発見したんです。


安田
心臓外科のどんなところに魅力を感じたのでしょうか。
國原
瀕死の状況で心臓外科に来た患者さんが、元気になって歩いて家に帰る姿を見ることができるところです。そこにはプラスしかない。例えば大腸がんがあったら、手術すると腸が短くなってしまいます。がんはなくなりますが、やはり機能的には多少落ちてしまいます。それが心臓外科にはありません。見ていて面白いと思いました。
もう一つ、心臓外科は理論的に分かりやすいということもありました。抗がん剤の効果はすぐには分かりませんが、心臓外科の薬は心臓や循環器に直接作用するのですぐに効果がわかります。医者として薬の使い甲斐があるわけです。
また、研究面でも面白みがありました。今でもわからないことは沢山ありますが、当時の心臓外科はまだそれほど研究が進んでいなくて、わからないことが一杯ありました。それが研究者としては魅力的でした。
2回に渡ったドイツ留学で人間的に成長できた


安田
日本での研究が進んでいなかったことでドイツへの留学を志したのでしょうか。
國原
研究というよりは手術の経験の量の問題でした。当時、日米で手術の数には10倍もの差がありました。遅れている分野では海外の新しい製品を輸入して真似をするしかないのと同じです。それくらい遅れていました。
私はドイツのザールランド大学に2回留学したのですが、1回目は無給でした。ドイツ語もできなかったので、向こうに行ってから2ヶ月間ドイツ語の学校に行ってから、病院に入りました。手術室ではなんとか通じましたが、病棟では患者さんが何を話しているかさっぱりわかりませんでした。
ただ、2年半の間に手術にはたくさん立ち会いました。いっぱい手術に入りたかったので、夜間でも土日でも呼び出してくださいとお願いしました。土日は採血もしました。週末には採血役の学生さんが不在なので、同僚からは助かったと感謝されました。人が嫌がる仕事を進んで引き受けることが信頼を得ることにつながるんです。
2度目の留学は北大に戻ってから4年経った頃で、立ち会っている手術の数が少ないのでもっと修練が必要だと考えたからです。今度はスタッフとして行きたかったのですが、1度目に周りから信頼されたことがプラスに働き、スムーズに受け入れてもらえました。皆さん「クニなら良いよ」と言ってくれたんです(「クニ」が自分の愛称でした)。
阪急東宝グループを創業した小林一三さんの「下足番を命じられたら、日本一の下足番になってみろ。そうしたら、誰も君を下足番にしておかぬ」という言葉が身に染みた瞬間でした。言葉が不自由でも、一生懸命やれば必ず報われるということをみなさんに伝えたいと思います。


安田
留学でどんな成果が得られたと思いますか。
國原
医学的には日本では珍しい大動脈弁形成術を学んで、今は私がそれを日本で広める役割を担っています。それが1番の収穫です。指導していただいたシェーファース教授が大動脈弁形成術の世界的な権威で、しっかり学ぶことができました。
日本ではまだ浸透していなかったので、帰国してからは教科書を書き、患者さんからデータを集めるレジストリを行い、豚の心臓とかで手術の方法を多くの医師に教えたり、全国の病院で手術の手伝いをしたりして、日本で大動脈弁形成術を広める活動に一生懸命取り組んできました。
それと同じくらい重要だったのは人間的に成長できたことです。日本はやはり競争社会なんですね。その分、人に対する思いやりや気遣いが薄れがちです。でもドイツでは自然にドアを開けてくれたり、車の運転では道を譲り合ったり、人を思いやる気持ちが感じられました。
私自身もドイツ語が得意でないことで、馬鹿にされたりすることはありませんでした。やはり大陸にある国で色々な人種が入ってくるために、他民族に対して寛容なんですね。日本はそういうことに慣れていないという側面があると思います。
北大に戻った時にパラグアイから留学生が来ていて、寂しそうにしていたので、私の方から声をかけて、論文を書く手伝いをしたりしました。そういう気遣いができるようになったのは、自分自身の留学での経験があったからです。
医工連携で開発したリングで大動脈弁形成術の普及を図る

外科医にとっての研究の面白さはどんなところにあるのでしょうか。


安田
外科医にとっての研究の面白さはどんなところにあるのでしょうか。
國原
内科医のように試験管で実験したり遺伝子を調べたりするのではなく、目の前の患者さんで研究するわけです。そのため分からなかったことがダイレクトにわかります。手術がどういう結果になったとか、こういう薬を使ったらこういう効果が現れたとか治療効果がすぐにダイレクトにわかって、臨床にフィードバックできます。そこが面白さですね。

治療効果がすぐにダイレクトにわかって、臨床にフィードバックできます。そこが面白さですね。


安田
臨床と研究の両立は大変ではないでしょうか。
國原
ドイツでも北大病院でも常に臨床しながら研究をしていました。特にドイツでは自分の足跡を残したくて、臨床も研究もしっかり取り組みました。振り返ると大学にいたことが大きかったと思いますね。研究の大事さが身に染みていたので、両方とも大切にするのが当然でした。
ただ、時間は作るしかありませんでした。私は夜11時までは病院にいようと決めていましたが、それでも学会で研究を多数発表しようとしたら時間が足りないくらいでした。土日はできるだけ家族といるようにする代わりに、平日は思い切り仕事に注力することにしていました。
初めてのドイツ留学の前はお金を貯める必要があって土日もアルバイトしていたので、よく離婚されなかったとは思いますが。留学という目標があったからこそできたのかも知れませんね。


安田
慈恵に来られたのはどうしてでしょうか。
國原
2度目の留学から帰国して2013年から六本木にある心臓血管研究所に勤務していました。その頃、当時の心臓外科の橋本教授と学会でご一緒していて親しくお付き合いしていました。それから4年ほど経った時に後任の主任教授を募集しているということでお声がけをいただき、慈恵に来ました。2018年6月のことです。


安田
今はどんな研究をされているのでしょうか。
國原
現在進めているのは、早稲田大学工学部との医工連携です。私が長年取り組んできた大動脈弁形成術ですが、未だに普及率は10%以下です。その原因は拡がった弁を締めるリングがないことにあります。欧米にはふたつあるのですが、日本では承認されていません。そこで日本で使えるリングを作ろうとしています。
左心房と左心室の間にある僧帽弁はそれなりに大きいので、弁尖も厚くて縫いやすいのですが、大動脈弁は本当に小さいので、扱いが難しいためになかなか普及しません。それを標準化するリングを市販して、多くの人が手術できるようにすることが今の私の目標です。すでに特許を申請しています。
その次は人に使えるように安全性などを確認しなければなりません。お金もかかる話ですが、幸い大型の研究費もいただけたので、進めることができそうです。機械弁と違って自分の大動脈弁が活かせるので、薬の心配もありません。退任するまでに実用化したいと思っていますが、実用化されたら未来が大きく変わります。
自分の時間を削ってでも苦にならない研究テーマを


安田
慈恵は研究がやりやすい大学でしょうか。
國原
素晴らしいところだと思います。研究にはお金が必要ですが、お金をもらうには実績が必要です。科研費をもらうにしても、こういう実績があって次にこれをしたい、ということを書かなければなりません。つまりニワトリと卵の関係なんです。
勿論、自分でお金を作り出したり、臨床のデータを研究材料にするという工夫するという方法もあります。先述の小林一三さんの「金がないから何もできないという人間は、金があっても何もできない人間である」という言葉は私の座右の銘ですが、なかなか簡単ではありません。
そこで慈恵では科研費をもらえない人に対してスタートアップの資金を出してくれます。あまり業績がなくても簡単な実験ができて、業績を生み出せるように、支援してくれているわけです。すごいなぁ、と思います。
他にも他の病院で働きながら学位をとる社会人大学院生という制度もありますし、普通の大学院生でも手当がもらえるなど、研究者にとっては手厚い大学だと思います。


安田
臨床と研究の両立のしやすさという点ではいかがでしょうか。
國原
それはどこでも変わらないと思います。臨床をきちんとやっていたら、昼間に研究する時間はありません。自分の時間を削るしかないんです。それが辛いという人もいますが、私はそれを苦に思ったことは一度もありません。自分が楽しくて取り組んでいるからです。
研究は自分がこの治療法がわからないところから始まります。どうしたらわかるのか、よくすることができるのかを考えて、どうすれば良いことを自分がわかれば、患者さんにもフィードバックできるので、苦にはなりません。
若い人がそういう自分が興味を持てて面白いと感じられるテーマを早く見つけられれば良いと思うので、勉強ということばかりではなく、夢を持てるような話をすることを心掛けています。教授を評価するアンケートで一位になった時は嬉しかったですね。


安田
研究者を志す学生に向けてアドバイスはありますか。
國原
医師を目指す人でもお金に目がいく若い人が多いのは心配です。美味しいものを食べて、綺麗な服とかカッコいい車とか買って、一時的にはハッピーかも知れませんが、そのあとはどうするのでしょうか。「人はパンのみにて生きるにあらず」という言葉がありますが、プライスレスなものこそが大切です。
書の詩人である相田みつをさんが「金が人生の全てではないが 有れば便利 無いと不便です 便利のほうがいいなぁ」という言葉を残しているように、お金はあると便利ですが、あくまでも手段です。人生には健康とか愛とか友情とか信頼とか、お金よりもっと大事なものがあるはずです。
その意味で研究はプライスレスであり、エンドレスな喜びをもらしてくれます。本当に瀕死の人が、歩いて帰るということに携わっていることは私の喜びです。皆さんもそういう研究テーマに出会ってください。臨床と研究の両立が全然苦になりませんよ。
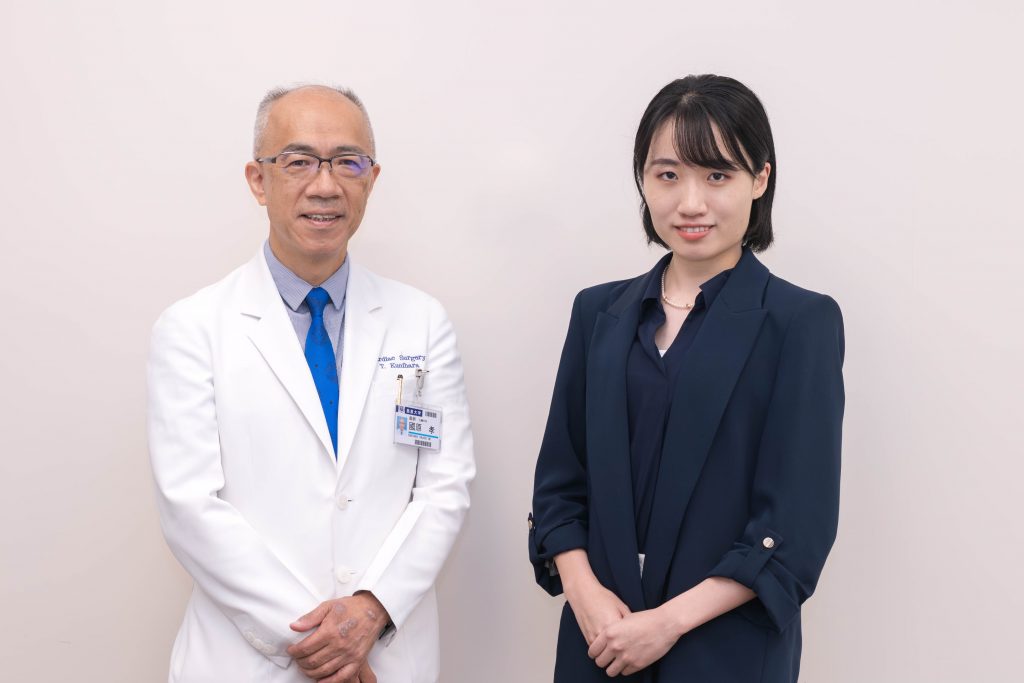
対談者プロフィール

國原 孝(くにはら たかし)
都立小石川高校卒業、北海道大学入学。北海道大学循環器外科ほか関連病院での研修を経てドイツ・ザールランド大学胸部心臓血管外科に9年間勤務。2013年12月から心臓血管研究所心臓血管外科部長を経て2018年6月より東京慈恵会医科大学心臓外科学講座担当教授着任。大動脈弁形成術の第一人者として臨床・研究を通じて国内の普及に努めている。また、患者さんには“One of them(大勢のうちの一人)” ではなく”Only one(唯一の一人)”として接し、患者さんの機能と生活の質の回復を目標として診療に従事している。

安田 眞ゆ(やすだ まゆ)
光塩女子学院高等科卒業。学生会、学生広報委員会に所属。3年次に学生会長、4年次に学生広報委員長を務めた。2年間の臨床実習では「迷いながら間違いながら」様々な経験を積み、その中で理想の医師像を見つけ、「同じ場所に向けて歩いて」いる。「選んできた道のりの正しさを祈」りながら、6年間の学生生活を終えようとしている。