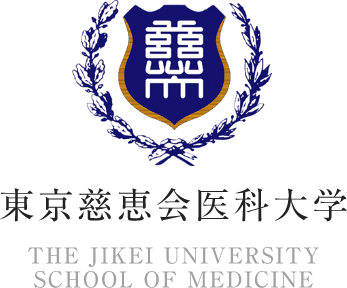第16回 当たり前と思わずに疑問を持つことが研究の道を切り開く原動力になる
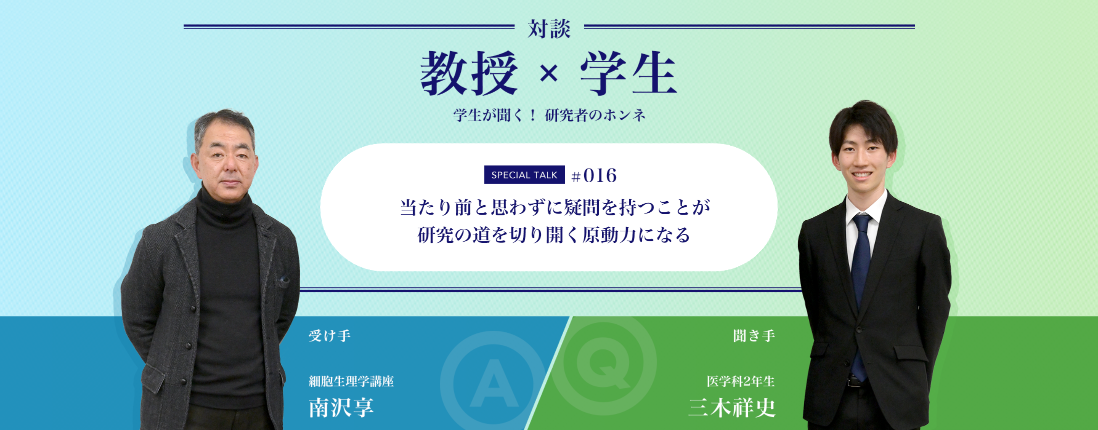


今回ご紹介するのは、小児科の臨床医からスタートして、今は細胞生理学講座教授として心臓血管系を中心とした生命現象の基礎研究に取り組む南沢亨さんです。基礎研究と臨床との関係や研究者としてのあり方などを語ってくれました。
感動的な発見がもたらすエキサイティングな喜び


三木
-なぜ基礎研究の道を選ばれたのでしょうか。
南沢
初めから基礎研究の道を目指したわけではありません。卒後9年間は大学病院などで小児科の臨床医として働き、1993年から鶴見大学歯学部の生理学教室で助手になって生理学の研究を始めたのが最初です。
大きな転機になったのは1996年からのアメリカへの留学です。カリフォルニア大学サンディエゴ校にポスドクとして4年半留学したのですが、その後半で循環器の分子生物学の研究に深く関わるようになりました。
もともとは臨床医として抱いた疑問を解決するには基礎研究が重要と考えて、少し経験してから臨床に戻るつもりでいました。留学先のボスだった教授から筋小胞体をテーマに研究するように指示されたことが本格的に基礎研究の道を進むきっかけになりました。


三木
-どんな研究だったのでしょうか。
南沢
細胞内の小器官である筋小胞体の機能を改善すると心不全が治ることを検証するという研究でした。遺伝子組み換え動物を使って研究したところ、それが確からしい成果が出て、その研究が認められて評価されました。このテーマについてはその後も視点を変えながら、継続して研究しています。
成果を上げられたのは、私にとっては偶然の産物でした。アメリカで研究をしていて新鮮だったのは、研究者たちが「エキサイティング」という言葉を使うことでした。臨床では例え難しい手術が成功してもこうした言葉は使いません。
しかし、研究では、これまでに誰もみたことがない、新しい発見をすることができます。それが感動や興奮を呼び起こすから、エキサイティングなんです。この研究の喜びを経験して、病みつきになりました。
それに加えて家庭の事情もありました。妻も医師で臨床医だったために、二人とも臨床医だと子育ても大変です。妻は臨床医を辞める気はないと言っていましたし、私は研究が面白くなってきた時期でもあったので、私自身は臨床ではなく研究の道を進もうと決めました。


三木
-臨床を通してどんな疑問を持っていたのでしょうか。
南沢
私が専門にしている小児循環器の疾患では心臓や血管に障害がある症例が多く、そういうお子さんは生まれながら心臓に障害を持っている形態的な異常がみられます。それを治療するには内科より外科の治療方法をとる場合が多いのですが、手術ができないような危険性を持っていることもあります。
こうした外科手術でも治せない心臓病を根本的に治療する方法もなく、そもそもなぜ奇形を持って生まれてくるのかという疑問が私自身は一番大きくて、その原因はなんだろうかとずっと考えていました。
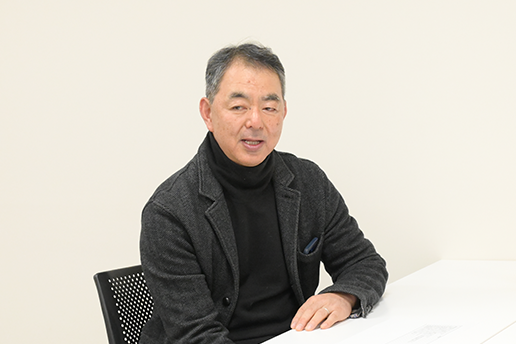
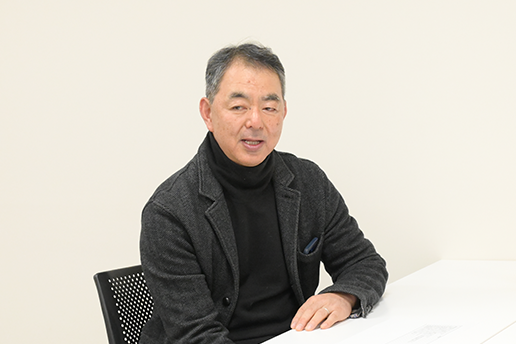
1990年の始め頃に、遺伝子解析や分子生物学的手法によって、その原因が少しずつわかるようになってきていて、特に海外にそういう場があったので、アメリカでその研究に取り組み、臨床に活かしたいと考えるようになりました。もう一つの私の研究テーマである動脈管の研究も同じです。この仕事は横浜市立大学に籍を移してから取り組み始めたものです。日本に戻って改めて小児循環器病に関わる研究をしたいと考えていた時に、私と研究をしたいという小児循環器医が研究に参加してくれたので、それでは動脈管の研究しようと一緒に取り組み始めました。

アメリカでの研究は新鮮で、大きな転機になりました。
基礎と臨床の間の溝を超えることに難しさが


三木
-先生の研究のゴールはどこにあるのでしょうか。また、今はゴールに対してどの辺りまできているとお考えですか。
南沢
ゴールは手術で治せないこうした病気を安全に治すことができる薬を作ることですが、まだ目標の50%も行っていません。多くの基礎研究は臨床との間に大きな溝があります。今はまだこの「基礎と臨床の谷」を乗り越えることができずにいます。
難しさは患者さんの特性にあります。動脈管の疾患は体重の少ない未熟児に多くみられます。疾患自体は心臓の病気としては治療がしやすい、手術で治る可能性が高いものです。
しかし、未熟児の患者さんに対しては手術が難しいのが実態です。当然、内科療法で治す方法が模索されてきました。実際に1970年台に治療薬が見つかったのですが、それでも治らないケースがあります。そこで新しい薬を作りたいと考えてきました。


南沢
一般的に言って、基礎研究で新薬についての効果を示すデータが得られても、最初のデータは動物実験によるものであって、人に対する安全性まではわかりません。人に対して使えるレベル、つまり臨床に持っていくにはより大規模な実験が求められ、大変になります。
さらに私の研究の場合は、患者さんが小児であることがネックになります。当然、治験はやりにくく、しかも患者数自体が少ない分野の研究です。創薬の段階まで持っていくことは経済合理性の面からも難しく、そこをクリアしても臨床へ進むには、ハードルはもっと高くなります。
これまでも大人に効くから子供にも効くだろうというアプローチはありますが、最初から子供向けの薬剤開発に取り組むケースはなかなかありません。一般的に小児の先天性疾患は似たような患者さんの数が少なく、開発コストに見合う成果が期待できないからです。
これまでの研究で私の中では灯りが見えていますが、創薬まで漕ぎ着けるにはまだ相当の時間がかかるため、ゴールまでの道筋は次の世代の人たちに委ねようと思っています。また、創薬やデバイスの開発には理工連携などチーム作りが必要です。こうしたチーム作りは私はあまり得意とするところではないのですが、異業種を巻き込んだチームワークは「基礎と臨床の谷」を乗り越えるための重要な戦略であり、効果的な武器にはなると思うので、若い人達には積極的に異分野の研究者と関わりを持つようにしてほしいです。

これまで研究者として苦労された点はどのようなことでしょうか。


南沢
研究面ではあまり苦労だと感じたことはありません。唯一あったとすると、留学して分子生物学に初めて触れた時です。当時の医学部では分子生物学を学ぶことが機会がほとんどなく、何もわからないまま留学した私は、全く知識が不足していて、それを埋めるのに苦労しました。
それまで9年間、臨床医を経験していましたら、それなりに自分は一人前の医者だという気分でいたのですが、留学したら大学院生から見ても何もわかっていない奴と見下され、奈落の底に突き落とされたような気分を味わって凹みました。
今考えると良い経験ですが、最初の一年は本当に苦労しました。ボスからは「帰国してもよいよ」くらいのことを言われました。
ただ、そこで4年半踏ん張れたのは臨床の経験があったおかげです。周囲の仲間からは「先天性心臓病に詳しいようだ」とボスにサポートする言葉を伝えてくれたりして、励ましてくれたことも大きな力になりました。
それがあって2年目に研究テーマを筋小胞体に変えてもらって成果を上げたことで、周囲からの見方も大きく変わりました。それがなかったら今の自分はいなかったと思います。

苦労したアメリカ留学も、9年間の臨床の経験があったおかげで踏ん張れました。
自分が重要だと思うことに集中して取り組んできた


三木
-研究者として特にどんなところを意識してきたのでしょうか。
南沢
重視しているのは、本当に自分のやりたいことをやるということです。研究を始めるといろいろなことが面白くなって、あれもやりたい、これもやりたい、になりがちです。今で言えば私がiPS細胞の研究もやってみたいと思ったりするようなことです。
でも私はこれまで自分にとって重要なことは何なのか、本当にやりたいことは何なのかを突き詰めて、取り組むようにしてきました。研究者としては、人がやっていなくて、自分にとって重要なことを研究テーマにすることが大切なんだと考えています。
例えば、動脈管の研究を突き詰めようとすると、弾性線維のことも研究するようになるのですが、そうすると弾性線維に富む皮膚や肺の研究もやりたいという気持ちが湧き上がったりします。でも自分はそこには踏み込まずに、心臓や血管に関わる研究に集中しようと努めてきました。
勿論、そうではない研究スタイルの研究者も多いと思います。なぜなら、生命系の研究では、心臓で解明したことが、脳や肺にも応用できたりして、一般化できるところも多く、臓器を特定して研究をする必要はないのかも知れません。
私自身は常に臨床で直せなかった子供を思い浮かべて自分の研究に打ち込んできました。小児と心臓を常に意識することで、自分がやるべきことから軸をずらさずに来れたのだと思います。


三木
-今担当されている細胞生理学講座の研究スタイルは他の研究室とどう違うのでしょうか。
南沢
他との違いは学生さんから見た方がよくわかるのではないでしょうか。ただ、テーマにはそれぞれの研究者の独自性を活かしてもらうようにしています。学生でも皆個別のテーマを意識しています。
私が本格的に研究を始めたアメリカ留学時代のボスはそういうスタイルでしたし、私もそれが良いと思っています。論文を効率よく生み出していくような生産性の良さはありませんが、一人ひとりがイニシアチブをとることが重要だと思っています。それが研究者としての成長を促すはずです。

慈恵は研究がやりやすい大学でしょうか。


南沢
YesかNoかと言われればYesです。研究がやりやすいことは必ずしも良い研究ができることとはイコールではありませんが、自分にとってはストレスなく研究に取り組めるところです。
ただ、大学内でもっとインタラクティブなやりとりがあった方が良いと思います。海外ではもっと研究室の垣根が低くて、研究者同士が積極的に連携して取り組んでいます。私と同じような小児の心臓を研究している研究者が少ないせいもありますが、それぞれが個々の研究の枠を持っていて、それを超えた活発な交流が少ないように思います。


三木
-学術情報センターや国際交流センターなどの責任者もされていますが。
南沢
研究者としては自分の研究に打ち込む時間を削ることになりますが、組織で働く以上頼まれればできるだけ引き受けて、割けるだけの時間の範囲で、できる限り真面目にやるようにしています。
大学時代の恩師がよく「7:3の法則」を言っていました。メインが7割、それ以外が3割という比率で世の中を生きた方が良いというわけです。意識しないとなかなかできないことですが、知らないことをやってみると勉強になりますし、自分の研究にも良い影響があるように感じます。


三木
-最後に研究者を目指す学生にアドバイスをお願いします。
南沢
研究者を目指す以上は不思議を感じること、疑問を持つことが大切です。今ある当たり前を当たり前のことと思っていては進歩はありません。
診療にはマニュアルがありますが、マニュアルに書かれていることをただ受け入れるのではなく、まず何故そうなのかと疑ってみることです。マニュアル通り治療をしても治らない人はいます。どこかに不完全なところがあるからです。そこに疑問を持ってください。不思議だと思う心が大切なんです。

対談者プロフィール

南沢享(みなみさわすすむ)
川崎市生まれ、茅ヶ崎市育ち。県立鎌倉高等学校、弘前大学医学部を卒業、横浜市立大学病院で臨床研修後に小児科に入局、循環器小児科医として約9年間臨床に従事する。その後、鶴見大学、カリフォルニア大学サンディエゴ校で基礎研究を始める。2000年に帰国後、東京女子医科大学、横浜市立大学、早稲田大学を経て、現職。専門は発達心血管生理学。趣味は大リーグ観戦、庭いじり。キュリアスジョージでいることを心がけている。

三木祥史(みきよしふみ)
東京学芸大学附属国際中等教育学校卒業。高校在学中、新型コロナウイルスに関する研究・論文執筆に携わり、医学研究に興味を持った。現在は1年次の選択科目「教養ゼミ」でお世話になった細胞生理学講座にて研究を学んでいる。学内では音楽部、陸上部、MEP、ジャズ研に所属。