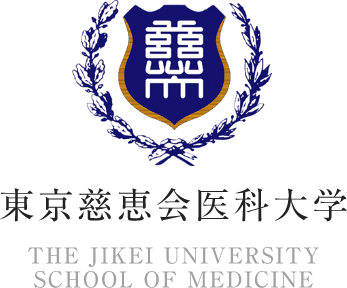第17回 立てるバッターボックスに立ち続けることで新たな学びと出会いの場が開けていく
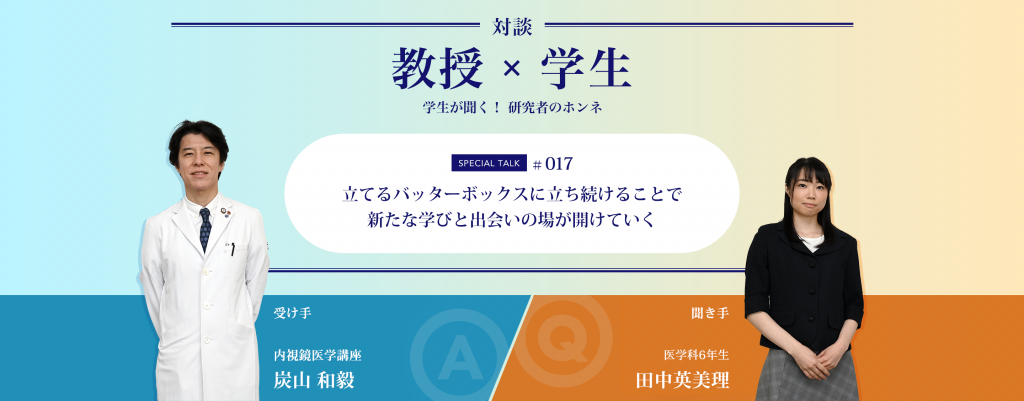


今回ご紹介するのは、内視鏡手術の機器や手技を開発することで患者さんの体の負担を抑えた手術を作り出している内視鏡医学講座教授の炭山和毅さんです。臨床実習で炭山さんのオペを見学して内視鏡の世界に魅了された医学科の田中英美理さんが、どんな想いで内視鏡の世界を極めようとしているのか伺いました。
医学とエンジニアリングで独自のポジションが作れた


田中
内視鏡の世界で国内初となる様々な取り組みをされていますが、そもそも内視鏡を専門とされたきっかけは何だったのでしょうか。
炭山
両親が医師だったこともあって、医師というのは私にとって身近な職業でした。お腹が痛い時に診てくれるのがお医者さんのイメージだったこともあって、消化器の医者になろうとは思っていましたが、内視鏡を選んだのは、先輩の話を聞いて勢いで決めました。
特に魅力を感じたのは、日本の内視鏡の国際的競争力が高いことを聞いたからです。入局当時、鈴木博昭先生という世界的に有名な教授がいて、研修医の時の休みを利用して、ドイツやアメリカの大学に送り出してくれました。
その時に最新のデバイスが開発されていく現場や、先進的内視鏡治療を見学することができ、内視鏡医学には様々な領域があり、幅広く新しい仕事にチャレンジできることを肌身で感じました。大学院では、高次元医用画像工学研究所に進み、それ以来、内視鏡機器や手技の開発に夢中になりました。
高次元医用画像工学研究所は、患者さんの画像データを活用し、新しい診断や治療法を研究するところで、工学部出身の研究者が多く、私自身もエンジニアリングについて深く勉強することができました。なにより、研究計画から論文を書くまでの苦労を学ぶ最初の機会になりました。
当時は、今のようにオンライン投稿システムがなく、紙と写真を学会誌に郵送し、3ヶ月くらい経って返事の手紙が来るような感じでとても時間がかかりましたが、論文として結実させることで、研究の喜びを実感できました。そのモチベーションで、大学院中に、3本論文を書きました。


田中
実習で先生のオペを拝見して感激しました。その基礎は大学院時代に培ったものなのですね。
炭山
元々理科や数学は大嫌いでしたが、大学院で科学技術に触れたことが大きな財産になっています。内視鏡は色々なテクノロジーの結晶です。光の波長の制御やレーザーなどの光学技術、そしてものづくりなどエンジニアリングの統合応用分野です。
私は学生時代から、ゴルフに打ち込み、自分が使用するゴルフクラブにはこだわりを持って探求してきました。内視鏡手技では、内視鏡を介して患者さんに触れることになるので、指や手からスコープや器具の操作感を繊細に感じ取ることが重要です。私は、内視鏡手技に真に精通するためには、内視鏡や器具の構造や機能、使われている金属についても理解しているほうがいいと思います。
大学院時代にエンジニアリングを学び、疑問があったら常に深掘りしてすることを習慣にできたことが、内視鏡の技術を身に着けることにとても役立ったと思います。
留学中にベンチャーと協業し新たなデバイスで新境地を拓く


田中
胃カメラを用いて胃を内側から縫い縮める内視鏡的スリーブ状胃形成術を日本で初めて実施できたのはなぜだったのでしょうか。
炭山
消化器がんの6割以上が内視鏡手術で切除されるようになっていますが、外科手術では、切ったら閉じますよね。一方、内視鏡では切ったら切りっぱなしで、あとは患者さんの自然治癒力に任せています。私が留学した時期、アメリカのメイヨークリニックでは食道や胃、大腸に穴をあけて腹腔や胸腔の中で手術を行うnatural orifice translumenal surgery (NOTES)の研究が盛んで、私自身も消化管の穴をどう閉じるかという研究に取り組むことになりました。2005年のことです。
そのころ、日本の大手光学メーカーが、海外の有名な先生方と一緒に穴を縫う技術を開発したのですが事業化をあきらめてしまいました。そこで、アカデミア発のベンチャーとして再出発することになったのです。まさにその現場に立ち会うことができて、ベンチャーキャピタルや起業家たちと一緒に仕事をすることができました。
その後、一緒に開発した内視鏡用縫合デバイスを用い、メイヨークリニックで私が所属していたチームは、肥満症の方の胃袋を内側から縫い縮め減量してもらう手術を開発しました。それが内視鏡的スリーブ状胃形成術です。
この手術を日本でも是非やりたいと考えていたのですが、デバイスが薬事承認されていなかったり、COVID19の問題があり手術の実例を見る機会が少ないなどの理由で、なかなか認可が下りませんでした。やっと実施できたのは2020年のことです。留学してすぐにこのデバイスに出会ってから実に15年の歳月が経っていました。


田中
メイヨークリニックではどう研究に取り組まれたのでしょうか。
炭山
私が所属していたのは、アドバンスド内視鏡チームのなかでも産学連携を進めるチームで、日本人で初めてのフェローでした。独自で新しいデバイスのプロトタイプを作ったり、世界の有名企業と一緒に様々な機器開発したりすることができ、とても楽しかったです。今日の研究や人間関係の重要な基盤にもなりました。
大学院時代の経験を活かし、2年弱の留学期間で研究プロコルを40本くらい書き、そのうち10本以上論文として発表することができました。残りも、何らかの形で機器や手技の開発に役立てられています。実験の前に仮説・課題を明確にし、プロトコルを書いて、実験結果のログをため、毎週カンファレンスで発表することを繰り返しているうちに、研究力も英語のプレゼンテーションのスキルも上達しました。
最も、ゴルフも学生時代以上に一所懸命取り組みました。毎日午後4時に研究を終わらせて、近くのゴルフ場に通い、休日には有名なパブリックコースに飛び込みで行ってプレーしました。あまり頻繁にゴルフをしていたので、ローカルの新聞に取り上げられたほどです。
異分野の人たちとの交流がアイデアをもたらしてくれる


田中
研究のアイデアはどんなところから生まれてくるのでしょうか。
炭山
私は消化器領域以外あるいは医学以外の人たちとの出会いやコミュニケーションを大切にしています。例えば、消化管の神経層に関する研究では、小児の病気であるHirshsprung病の手術に役立つかもしれないことを知り、小児外科の先生と神経を可視化する研究開発に取り組んできました。今は、慈恵医大と連携している東京理科大の先生と一緒にデバイス開発を行っています。
ある内視鏡治療用のデバイスは、大阪大学の外科の先生とシンガポール政府を訪れた際、大阪商工会議所の人たちと出会ったことがきっかけとなり生み出されました。仕事終わりに、食事をしながら彼らと日本の医療機器開発の未来に関する話をする機会があって、その結果、関西の優れたモノづくり中小企業とコラボレーションする機会を得ました。2014年には、すぐに使いたいような器具を迅速に作ってもらえる産学医工連携チームが慈恵医大に発足しました。その活動から生まれた早期消化管癌の内視鏡切除用デバイスは、いまでは世界的医療機器メーカーに販売してもらっています。医師は機器開発の発明者にもなれますが、同時に、エンドユーザーでもあるので、販売や出口側の戦略にも強みがあります。若手の皆さんにも、日ごろの診療から思いついたアイデアを、ぜひ製品として形にする喜びも味わってもらいたいと思っています。


田中
臨床実習では食物の逆流などを起こす食道アカラシアのPOEM治療のオペも拝見しました。POEMは先生が編み出したthird space endoscopyという術式が取り入れられていると聞きました。
炭山
米国留学中、NOTESという消化管に穴をあけて手術をする研究をしていた時に、消化管外に安全に出るために開発した方法が、世界的に食道アカラシアの治療法として普及しました。留学前、慈恵で早期癌の内視鏡切除をする際に、粘膜下層を剥離する技術を身に着けていたので、その技法を応用し、内視鏡的に粘膜下層の中にトンネルを掘って、その奥から筋層を切開して、内視鏡を外に出す方法(submucosal endoscopy with mucosal flap valve法)を考案しました。その方法を使えば、上に被った粘膜で筋層の穴が覆われているため、粘膜側のトンネルの入り口をクリップで筋層に張り付けて閉じることで、消化管の内容物を外に漏らすことなく閉鎖することができます。食道アカラシアの患者さんは、食道下部の筋肉が緩まないために狭窄を起こし食べ物が呑み込めません。従来の標準治療では、狭窄している食道の筋層を外から外科的に切開する方法が行われてきました。一方、私が開発した粘膜下層にトンネルを掘ってから筋層を切開する手技を食道で使うと、外科治療と同じことを、体の中から体表を傷つけることなくできることに気が付きました。今では、内視鏡のワーキングスペースとして、消化管管腔が第一空間、腹腔・胸腔が第二空間、そして粘膜下層に人工的に作った空間が第三空間つまりThird spaceと呼称されるようになり、Third space endoscopyは、内視鏡治療の新たな1分野として世界的に認識されるようになりました。私は、20年前の動物実験で、そのきっかけを作っただけですが、今では世界中の患者さんのお役に立てて本当に幸せです。

慈恵医大は研究がしやすいところだとお考えですか。


炭山
アメリカでは動物実験用の臓器を摘出するのも大変でした。どこかのラボで、動物の解剖をするときは、ポケベルで連絡してもらえるようにして、自分で解剖し臓器を確保していました。
慈恵医大の研究環境は、都心の真ん中に大動物を扱えるラボがあり、交通の便もいいので海外企業も慈恵に来て研究しています。新しいことにチャレンジする環境としては、メイヨークリニックよりも優れた環境だと言えますね。
臨床医学の医師に求められる学、術、道の3つのバランス


田中
研究と診療の両方をされていますが、やりがいはどう違うのでしょうか。
炭山
私にとって一番大切なことは、やはり臨床で患者さんに喜んでもらえることです。早期に病気を見つけるためには、学問として病気を勉強するだけではなく、数多くの患者さんに触れ、病める部位を異常と思える感覚を、骨身にしみ込ませることが必要です。問診から治療まで、自分の五感を研ぎ澄ましておくことを常に心がけています。
私にとって青山学院中高の大先輩でもある、慈恵医大元学長の阿部正和先生は、臨床医学について「学と術と道」という言葉を残されています。私は、この言葉を噛みしめ、後輩にも伝えています。学:学問は、未来の多くの人の役に立てるよう、他の人が再現できる客観的評価に耐え得るものであるべきです。術:先人が確立した技術を学び、その方法を習得することが、患者さんを診る基礎になります。道:人道や自分の技を極める道、道とは、個の力を追求するために主体的に努力し続けることだと解釈しています。医師には、この3つの素養が求められていて、それが医師のやりがい、生きがいになっているのではないかと思います。
例えば、学術的データとして成功する確率が90%の手術だとしても、残念ながら、10%の失敗にあたってしまえば、その患者さんにとっての失敗率は100%です。医療は、このように確率や学問では割り切れないものなので、学と術と道の全てを持って臨むことが必要なのだと思います。
臨床で患者さんと過ごす時間から、疑問や課題が見つかり、それが研究テーマとなって学問になります。その研究が臨床で患者さんの役に立てば最高です。


田中
将来についてはどんな目標をお持ちでしょうか。
炭山
昔から遠い先の目標を立てるのは避けてきました。自分も社会も遠い未来にどうなるかは誰もわからないからです。自分で明確に目標を立ててクリアできるのは、せいぜい2、3年先のことではないでしょうか。これまでも、その時々で私に求められていることに柔軟に対応できるよう努力してきました。
例えば、国の研究予算をいただき内視鏡用AIの開発に取り組んでいますが、実は大学院生の研究テーマを探していたときに、昨今のAIブームがやってきたのです。わたしが医者になったときにAIが内視鏡と関係することになるとは夢にも思いませんでした。
ただし、わかっている未来については長期的なビジョンをもって対応しようと意識しています。人口が減少し若者の割合が減っていけば、日本のヘルスケアシステムが立ち行かなくなるところも出てきます。日本でそれを解決できれば将来、海外でも役に立つでしょう。AIやロボットの応用、デジタル技術の活用は当然ですが、それ以外の研究や人材育成においても、この回避できない課題に真正面から取り組むべきだと思います。
日本で、自分のアイデアが活かすことができなくても、海外では有用なことがあります。そのコミュニケーションツールとして、英語は便利です。私自身は英会話をきちんと勉強したことがなく、最初は学会で発表することにすら不安がありましたが、英語をうまく話すことが重要ではなく、話す内容が大事だと気付き、とにかく堂々と大きな声で話すようにしたら伝わるようになりました。今では、英語は自分のキャリアにとって、強みになっています。

短いタームで目標を立てて挑戦し続けていくことが大切


田中
これから研究者を目指す人に向けてアドバイスをお願いします。
炭山
SNSが生活の一部となっている多くの学生を見ていると、発信を通して、他の人に認識されることに喜びを覚える人が増えているのではないかと感じています。そのような人は研究者の素質があります。研究をはじめていい結果がでると、学会や論文で発表し、今まであったこともない同じ研究領域の仲間に認識されるようになります。それが研究において、いわゆる承認欲求が満たされる瞬間です。研究は勉強とは違います。自分のやりたいことを考え、検証し、その成果を皆さんに認めてもらうというサイクルの積み重ねです。ただし、論文として、文章を書いて正確に事実を伝える技術は、短いセンテンスや写真の印象で伝えるメッセージとは異なります。文章を書くという作業は、医師としても、自分の考えを整理し、患者さんに正確に伝えたい内容をお話する際に、非常に役立つ技能だと思います。研究は楽しいものですし、自分に対する未来への投資だと思って気軽に取り組んで欲しいです。最初は、成果が出やすいテーマから取り掛かることをお勧めします。コツコツと人に認められる成果を積み上げていくことで、研究は続けられるものです。
とにかく大事なのはバッターボックスに立つことです。ヒットやホームランを打てるかどうかは練習次第ですが、バッターボックスに立たなければ何も始まりません。人も運も機会も、一期一会そのものです。とにかくチャレンジして、一生に一度のタイミングを逃さないで欲しいと思います。

対談者プロフィール

炭山和毅
(すみやま かずき)
青山学院高等部から慈恵医大に入学。ゴルフ部で結構活躍した後、1998年に卒業し内視鏡科に入局。大学院は、高次元医用工学研究所に所属し、以来、機器や手技の開発研究に注力している。2005年には米国Mayo Clinicへ留学。2015年に内視鏡科(現内視鏡医学講座)教授に就任した。モットーは、立てるバッターボックスには必ず立つ。趣味は今もゴルフ。

田中英美理
(たなか えみり)
筑波大学附属高等学校卒業。入学後、分子疫学研究部でユニット医学研究を選択、大学院講義も活用しながら研究を行う。厚生労働省業務体験や留学等を経験、臨床や研究・行政といった様々な角度からの医療貢献を学ぶ。臨床実習で炭山先生のオペを見学し、内視鏡の魅力に魅了された。カリキュラム委員会や卓球部、疫学研究会等に所属する他、研究をテーマとした学内向けイベントを主催。