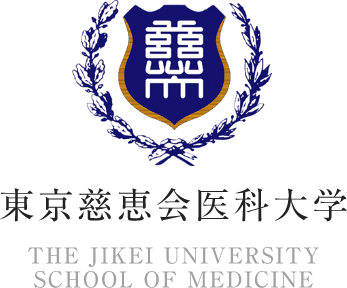第18回 目の前の命を救うために循環器科から救急医療の道へ
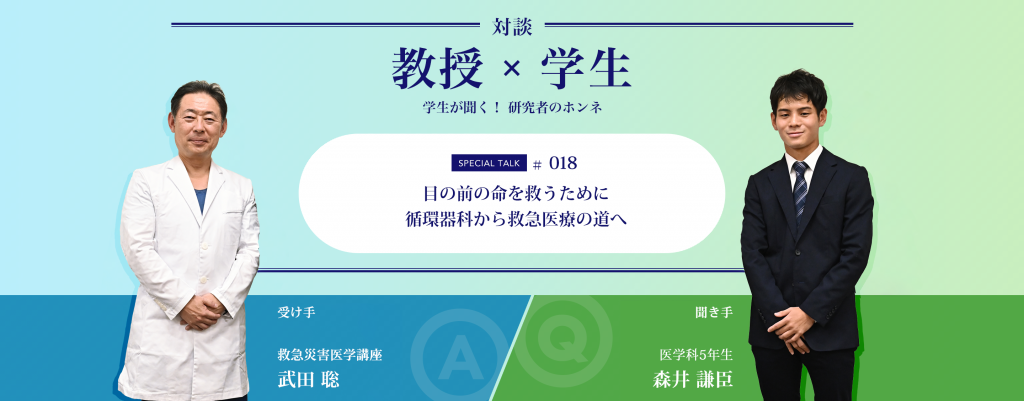
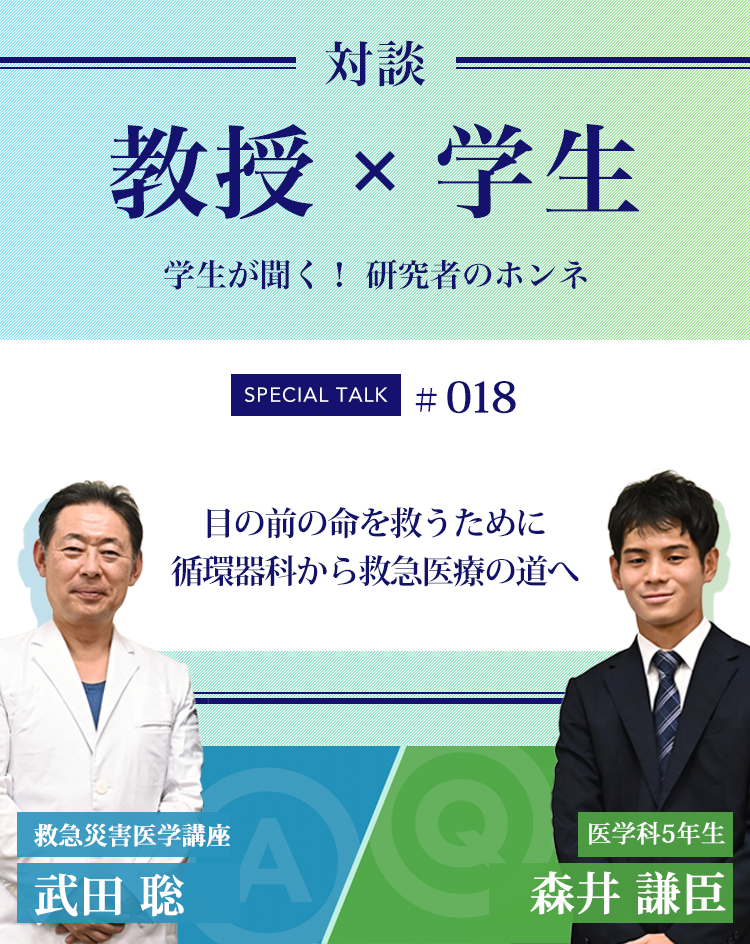

今回ご紹介するのは、救急科(循環器)の研究者であり、AEDの普及など救急医療に長年取り組んできた、慈恵医大救急災害医学講座主任教授兼救急部診療部長の武田聡さんに話を聞きました。
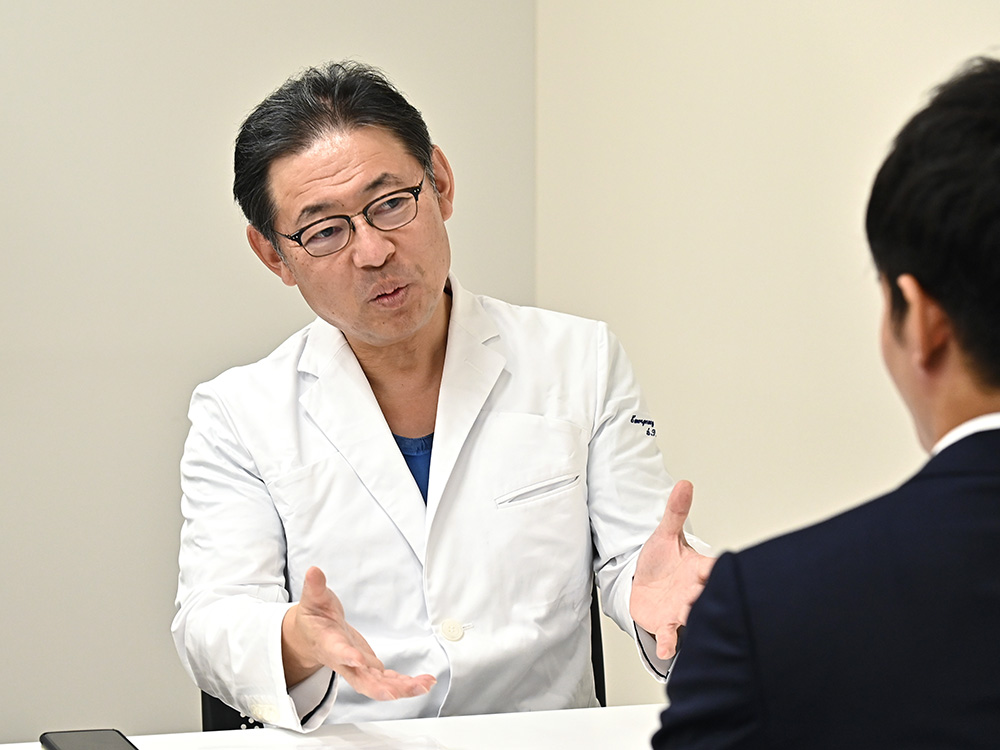
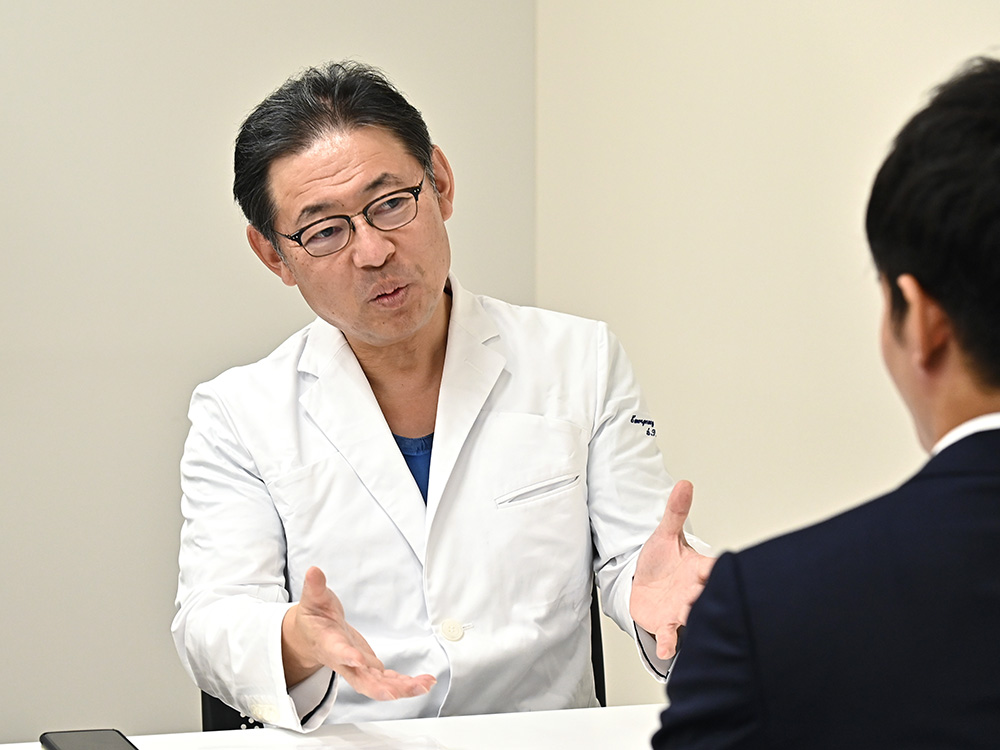
森井
―医師を目指されたきっかけについてお聞かせください。
武田
私は山梨県甲府市の出身で、雄大な富士山の麓の豊かな自然に囲まれた穏やかな環境で育ちました。幼い頃から、医師として地域医療に貢献する叔父の姿を間近で見てきたことが、医師を志すきっかけとなりました。
叔父の診療所は、母の実家がある山梨県韮崎市にありました。そこは、まだ街灯も少なく、夜には満天の星空が広がるような、のどかな田園風景が広がる地域でした。診療所は、母の実家の隣にあり、地域の人々にとって、なくてはならない存在でした。
私は、幼稚園に入る前から、祖母に会いに母の実家に遊びに行くたびに、叔父の診療所の様子を興味深く観察していました。叔父は午前中に診療所で診療し、午後は往診に出かけるのですが、その往診にもついてきました。
診療所の看板に「24時間いつでも呼んでください」と書き、患者さん一人ひとりと丁寧に向き合い、温かい言葉をかける叔父の姿は、幼い私の心に深く刻まれました。その姿を見ていて、いつしか私も医師として、人々の健康を支えたいと強く思うようになったのです。
また、従兄弟たち三人が医師と歯科医だったことも、医療の道を志すことを後押ししました。そのうちの1人は本学の卒業生で、栗原理事長と同級生というご縁もありました。私の医師への憧れはますます強くなっていきました。


森井
―地元の山梨医科大学医学部に進学されていますが、学生時代はどのような活動をされていたのでしょうか?
武田
部活は慈恵ほど充実してはいませんでしたが、夏は軟式テニス、冬はスキーと、四季折々のスポーツを楽しみながら、体力と精神力を鍛えました。またオーケストラ部ではトロンボーンを担当し、3つの部活動を掛け持ちで楽しんでいました。
部活動を通して学んだのは、チームワークの大切さや、目標に向かって努力することの大切さです。これらの経験は、医師として、多職種の医療スタッフと連携し、患者さんのために最善を尽くす上で、非常に役立っています。
大学卒業後は、山梨大学医学部循環器科に、ダイレクトに大学院に、進みました。当時は、初期研修医としてのスーパーローテーションではなく、最初から志望科に進む体制でした。
最初は救急医療をやろうと思っていたのですが、当時の救命救急センターでは、救急に運び込まれる患者さんは、交通事故や殺傷事件の被害者が多く、自分だけでは助けられない非常に重篤な症例ばかりで、一体私に何ができるのか、真剣に考えました。そして、選んだのが循環器科でした。循環器疾患の患者さんであれば、自分1人であっても、心筋梗塞で倒れた患者さんに電気ショックを与えたり、心臓カテーテル治療をしたりするなど、救命できる可能性があると考え、まずはこれをやろうと考えました。


森井
―大学院に進もうと考えたのはなぜなのでしょうか。
武田
循環器について深く研究し、学位(医学博士)をとろうと考えたからです。患者さんの命を救う救急医療をライフワークにしていくためには、研究は必須です。当時はまだ大学ができたばかりで、大学院といっても研究体制が充実していない状況でしたが、博士過程2年の時に「慈恵医大へ国内留学してはどうか」という話をもらいました。
当時、今の葛飾医療センターには当時の循環器科の研究では国内トップクラスの永野允先生がいらっしゃり、慈恵の循環器科は当時から国内でも有名でした。慈恵に移った私は仲間と一緒に実験を行い、研究論文を書く日々を過ごしました。
大学院では、ラットを用いた心筋梗塞の研究を行いました。具体的には、ラットに心筋梗塞を起こさせ、心室細動の発生メカニズムを解明する研究です。一度心筋梗塞を起こしたラットの心臓(冠動脈)に再び血液を流す「再灌流」で心室細動を誘発し、どのような薬剤を投与すれば心室細動を抑制できるか、心筋のダメージを軽減できるか、などを調べていました。
AEDの普及によって急速に変わった
心肺停止の救命率をもっと高めたい


森井
―先生は、現在でも心肺蘇生やAEDの普及に尽力されていますね。
武田
ずっと自分が志す同じ道を進むことができたのは、大変幸せだったと感じています。一昨年からは救命救急センター長も兼務しています。みなとシティマラソンで倒れた人を心肺蘇生とAED(自動体外式除細動器)で救うこともできました。
心肺蘇生のやり方は昔とは変わってきました。最初は胸骨圧迫と人工呼吸の比率を5:1でおこなっていましたが、その後は15:2になり、今は30:2になっています。私は心肺蘇生の激動の20年間をずっと現場で見てきて、その流れを目の当たりにすることができました。
この20年で救命率も大幅に向上しました。「やればできる」という想いを今も強く持っています。

転機になったのはどんなことなのでしょうか。


武田
やはり2000年代前半からのAEDの普及です。蘇生法自体が変わりました。それまでは助からなかったような人を助けられるようになり「自分がやってきたことが役にたつ」と確信しました。
海外の国際線の飛行機にはAEDが搭載されているのに、日本の航空会社の飛行機には搭載されていないことが問題になり、2001年に日本航空の国際線の機内に配備されたのが最初です。当時、AEDを早急に日本に入れるように交渉したのは、慈恵ご出身の日本航空の産業医たちがでした。慈恵の先生方は日本へのAED導入にも非常に重要な役割を果たしたことになります。
ただ、電気ショックをするAEDを誰が使えるようにするのか、は難しい問題でした。当時は、医師のみが使うべき、という声もありましたが、結局客室乗務員にAEDの使用法を習得していただき彼ら彼女らが使用できるようになり、2003年からは救急救命士も医師の指示が無くても使えるようになり、2004年からは一般市民も使うことが許されました。
それ以来、救急医学講座が中心となり、日本でのAED導入のサポートを続けてきました。私も公益財団法人日本AED財団の常務理事を担当させていただき、引き続きの普及啓発に努めています。
また慈恵では、文化部の「慈恵CPRスタディグループ(JCS)」がリードして慈恵内での普及啓発も続けてきました。全国医学生BLS選手権大会にも積極的に出場し、日本蘇生学会では3年連続でビデオ最優秀賞を受賞したりしています。こうした経緯から、臨床現場や教育現場ではもちろん、医療系学生の中でも、「AEDと言えば慈恵」と言われるようになっています。
AEDの普及は、まさに救急医療における革命でした。それまで、心停止の患者さんを救えるかどうかは、医療従事者が到着するまでの時間に大きく左右されていました。しかし、AEDの登場により、一般市民でも迅速に救命処置を行うことができるようになり、救命率の向上に大きく貢献しています。
私は、大学病院や地域で、AEDの講習会を数多く開催してきました。その中で、AEDの使い方を学ぶだけでなく、心肺蘇生法の重要性や、救命処置に対する意識を高めることにも力を入れてきました。


森井
―AEDの普及によって、救命率はどう向上したのでしょうか?
武田
年間約7~8万人が心停止で亡くなっていますが、そのうち約2万5千人は誰かの前で倒れています。AEDの普及と市民による救命処置の増加によって、救命率は着実に上がってきています。
しかし、現状に満足しているわけではありません。AEDの普及率は向上しているものの、実際にAEDが使われるケースはまだまだ5%と少ないのが現状です。装置自体は65万台配備されているので。もっと救命できるはずです。

課題はAEDを使うことに抵抗がある人が多くいることです。


武田
AEDは、電気ショックが必要な人にだけ電気ショックを流すように設計されています。そのため、AEDを使うことで、患者さんを傷つけてしまうことを心配する必要はありません。むしろ、AEDを使わないことで、救命の機会を逃してしまうことの方が大きなリスクです。
ただ、「勇気を持って使いなさい」と言われることもありますが、実際にAEDを使った人のほとんどは、一度はトレーニングを受けているのです。勇気だけでなく、正しい知識と使い方を事前に身につけることが重要です。救命処置に対する意識改革など、さらなる取り組みが必要だと感じています。
客観的な医療シミュレーション教育を通して現場で役に立つ医療人の育成を目指す


森井
―研究者としての思い出にはどんなことがあるのでしょうか。
武田
2006年に慈恵の講師になった後の留学です。2010年からピッツバーグ大学メディカルセンター(UPMC)に2年間留学しました。UPMCには当時から確立された医療シミュレーション教育があり、それを身につけることができました。
私はUPMCで習った医療シミュレーション教育とラピッドレスポンスシステムを慈恵に導入しました。ラピッドレスポンスシステムは院内で心停止を起こさせないようにするもので、安全安心な病院であり続けるためにも非常に重要です。
一度心停止になると身体に影響が残り障害を残す可能性もありますが、数時間前にある予兆に気づくことができれば、それを回避できます。慈恵がより安全安心な病院であり続けるために、私が留学で学んだことが役立てば、こんなに嬉しいことはありません。
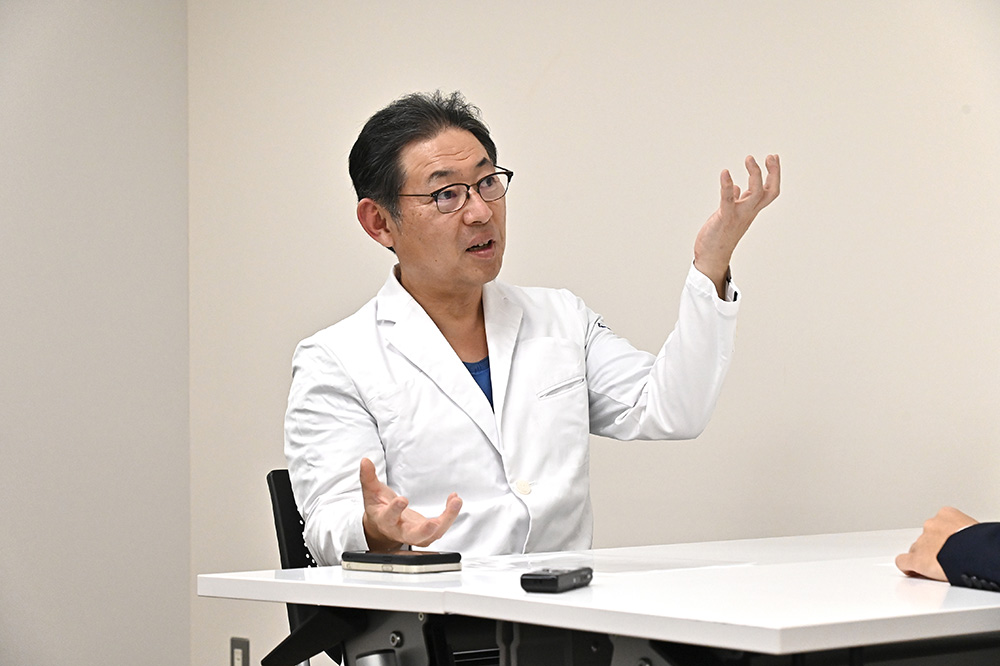
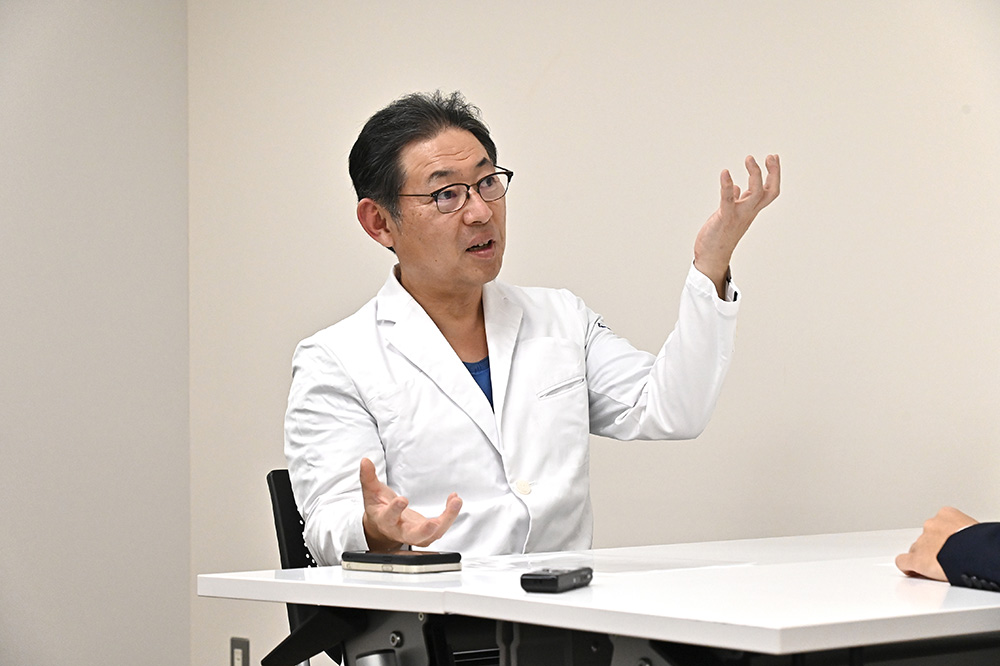
森井
―今後の研究についてはどのような展開をお考えでしょうか。
武田
私の研究テーマは大きく2つです。心停止の患者さんをどう助けるのかがひとつ。基礎研究から始まり今は臨床研究に取り組んでいますが、心肺蘇生の領域はまだまだ発展途上で研究の余地が多く残っています。
もうひとつが医療シミュレーション教育です。昔は患者さんで経験するしかありませんでしたが、今はしっかりしたシミュレーターなどがあります。どう教えれば、現場で役に立てる医療人が育てられるか、が研究テーマです。
そのためには学生たちがもっと気軽にシミュレーショントレーニングができるシミュレーションセンターが必要だと考えています。シミュレーターなどを使用した客観的なシミュレーショントレーニングでの評価がないと、その技能や手技は改善ができません。慈恵には多くの機材があり、立派な指導者も数多く揃っています。こんな医学部は他にありません。
2005年に設立された慈恵の救急医学講座は、今年2025年に救急災害医学講座と改名し、設立20周年という大きな転換点を迎えました。救急ICUもオープンし、外科チームも加わり、よりパワーアップした体制となりました。目の前にある命を救いたいという私自身のライフワークのため、ぶれることなく取り組んでいきます。慈恵の救命救急を飛躍させて、港区を世界一安全な街にする、東京都を世界一安全な街にする、日本を世界一安全な国にすること、が私の願いです。
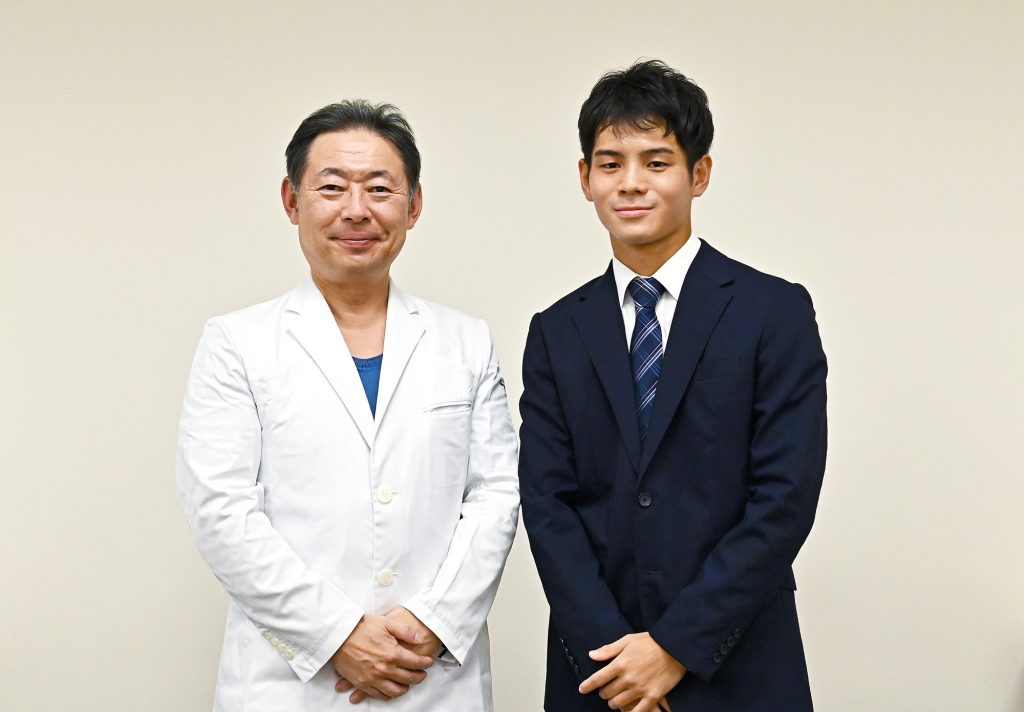
対談者プロフィール

武田 聡
(たけだ さとし)
山梨医科大学卒、同大学院修了。国内と海外の留学を含む循環器科医としての経験を持ち日本救急医学会や日本循環器学会の専門医として活動。2016年からは東京慈恵会医科大学での救急医学教授および附属病院救急部の診療部長として、また2023年からは救命センター長を兼任。公益財団法人日本AED財団の常務理事や、臨床教育開発推進機構の理事なども務める。

森井 謙臣
(もりい けんしん)
開成高校卒。叔父の院外心停止をきっかけにプレホスピタルケアの重要性を再認識し、キャプテンを務めるJikei CPR Study Groupの活動を通してBLSの錬度向上と一般の方々へのCPRの普及を図っている。ほかに、5年次から硬式野球部に所属し日々体の衰えを実感している。BUMP OF CHICKENをこよなく愛する。