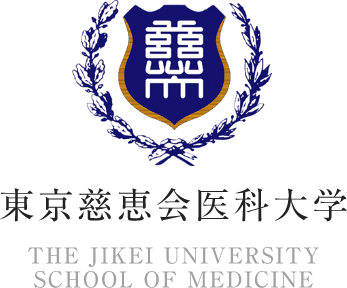第2回 臨床と研究の両方を行き来することで研究者としての一生のテーマが見つかる
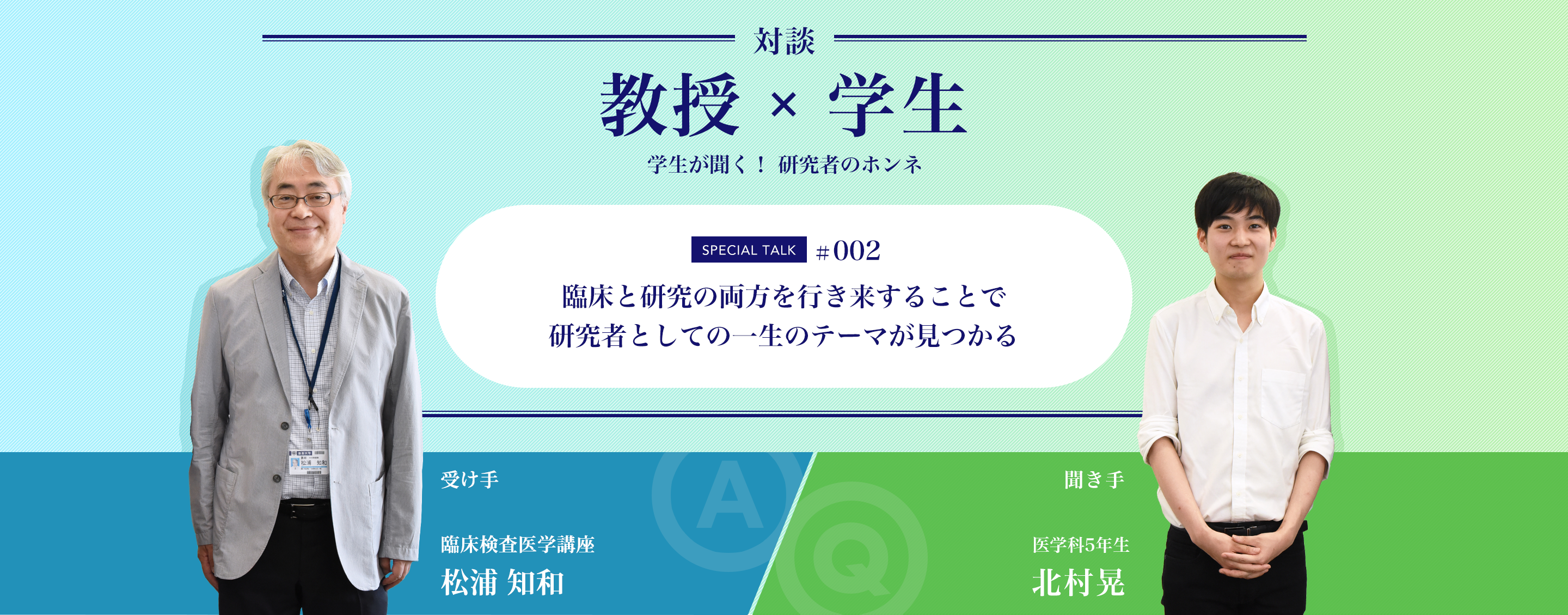


本学では、疲労が起きるメカニズムを解明するために、運動療法や栄養療法などの研究に取り組んでいます。その評価項目の一つに挙げられているのがビタミンDの濃度です。本邦初の臨床検査用全自動高速液体クロマトグラフィー・質量分析システムを利用して、ビタミンDの基準範囲の設定に取り組む臨床検査医学講座教授兼SI医学応用研究センターセンター長の松浦知和さんに、研究者としての考え方や研究のやり甲斐について話を聞きました。
普通の臨床医を目指して医学生に


北村
-いつから研究者の道に進もうと考えられるようになったのでしょうか。
松浦
あまり意識しないままいつの間にか、という感じです。父が開業医だったこともあって、入学した時には将来は臨床医になるんだろうと考えていました。当時でも多くの学生は臨床医を目指していたと思いますよ。
ただ、実習の同じグループに3年生の時から研究を始めていた学生がいて、それがきっかけで研究に興味を持って、少し研究させてもらおうと考えるようになりました。そこで、5年生の終わりくらいに彼にお願いして栄養学の研究室を訪ねました。
でもその時は特に研究者になろうとか考えていたわけではなくて、実際には医師になってから研究に触れる機会があり、その流れで本格的に研究取り組むようになったんです。ちなみにその学生というは、今の松藤学長です(笑)。


北村
-そうだったんですね。しかし、栄養学の研究室で研究したことが今の先生の研究に繋がっているような気もしますが。
松浦
当時は、まず実験をやってみたということだけですね。今考えると簡単な実験でしたが、実験の内容よりも、当時の林教授に「上手くいったね」と褒められたことが、その後も研究をやってみようかなと思わせてくれました。

きっかけは実習で同じグループにいた今の松藤学長でした
部活動で生活にメリハリがついた


部活動と学業の両立はハードではありませんでしたか?
北村
-慈恵の医学部は部活動も活発です。先生はバスケット部だったと伺いましたが、部活動と学業の両立はハードではありませんでしたか?
松浦
確かに週3回は夕方国領キャンパスに行って部活動に参加していましたから、傍目に見ればハードに見えるかも知れませんね。ただ、慣れるとそんなにハードだということはなくて、むしろ日々の生活にメリハリがついて良い感じでした。
今も昔も「勉強する時に勉強すれば良い」という自由さが慈恵の医学部にはありますが、私は授業に出ている方でしたね。


研究者として自分で考えて何かを創っていく意識が大切ですね。
北村
-私自身は受験校出身で、中高生時代は自分の好きなようにはできませんでした。それだけに、個々の裁量に任せてもらえるからというのが、慈恵を選んだ理由の一つです。
松浦
基本的に能力が高い人が多く、クラブ活動を主体にしていても、後でちゃんと取り戻せば良いという風潮は強いですね。実はそれが医師を志す学生にとっては大切なことなんです。
入学してくる学生さんたちは非常に厳しい受験勉強をしてきた人が多いだけに、自分で考えて何かを創っていこうという訓練が不足しています。入学してからの6年間でそれをきちんと学ぶことは、医師としては必要なことです。臨床では診療チームの要になるわけですし、研究者なら自分で研究テーマを設定して追求しなければならなくなりますから。
臨床と研究の両立を研究者としての強みに


北村
-どんな経緯で研究活動に入っていったのでしょうか。
松浦
5年生の終わりに栄養学の研究室で実験をさせてもらった後に、今の学長の松藤先生に「肝臓の研究をやりたい」と相談したんです。父が肝臓病で他界したことも影響していました。
人を介して第一内科のグループのトップの先生を紹介してもらったのですが、その先生が強烈な人で、初対面で「研究はそんな甘いものでない」と30分も怒られました。でもその後「じゃあ肝硬変の研究でもするかね」とおっしゃってくださった(笑)。そこで動物で肝硬変のモデルを作ることになり、大学院に進学したのです。

大学院生としてずっと研究に取り組んでいたのでしょうか。


松浦
昼間は研修医と同じことをやって、夜は研究という感じでした。当時はその辺りはごちゃ混ぜだったんです。今の4年間じっくり研究できるという大学院の環境は大変良いと思います。
研究者にとっては、単に実験をするということだけではなく、論文をまとめて、出版まで持っていて、最後の学位審査をちゃんと受けるということまできちんとやることが必要です。それを考えると今の制度はよく出来ています。


北村
-確かに今の慈恵には研究しやすい環境が整っていると思いますが、他大学と比べて優っているのはどういう点でしょうか。
松浦
臨床の近くにいながら研究ができることです。臨床をやってから研究、研究をしてから臨床という行き来をすることを「トランスレーショナル・リサーチ」というのですが、臨床で患者さんを診ていると、研究ではわからない疑問点が見えてきます。
疑問を持つと研究を続けられます。一生研究し続けられるテーマが見つかってくるものです。そういうテーマを見つけることが研究者にとっては大きな財産になっていきます。

一生研究できるテーマを見つけることが研究者にとって大きな財産になります。
伊東細胞の研究からビタミン、バイオ人工肝臓へ


北村
-先生もそういうテーマを見つけることが出来たのでしょうか。
松浦
卒業した後に与えられたテーマは肝臓の伊東細胞の研究でした。伊東細胞を肝臓から分離して培養しました。伊東細胞はビタミンAを蓄えるんです。
肝臓の線維化の研究のために、培養伊東細胞のビタミンA蛍光を観察していて、光っているビタミンAがとても綺麗に見えて、どうもビタミンAの研究も面白そうだと思うようになって、同時並行で研究するようになりました。
しかも、当時のビタミンAの研究はそれまでとは違う局面に入っていました。それまでは栄養学的に捉えられていたものが、レチノイン酸核内レセプターと言うのが見つかって、遺伝子の転写を制御することがわかってきて、新しい分野の研究として注目され始めていたんです。
例えば、急性前骨髄性白血病は、今ならレチノイン酸とかを使ってある程度治療が可能ですが、30年前は米国の研究グループが、ビタミンAを投与することで分化誘導治療ができることを突き止めたりした時代だったんです。

そこからどんな研究活動をされたのでしょうか。
松浦
2年間アメリカのフィラデルフィアにある今のペンシルバニア医科大学に留学して、肝臓におけるビタミンA代謝に関する研究をして、帰国してからは研究室で樹立したヒト肝臓がん細胞の株を使ってバイオ人工肝臓を創る研究に取り組みました。
それまで細胞の研究には動物細胞を使っていたのですが、肝臓の代謝は人特有のものだけに違ったアプローチが必要だったんです。そこで私の所属した研究室では、ヒト細胞株を樹立する研究が行われていました。研究の過程でその細胞でバイオ人工肝臓を創り、ブタの急性肝不全モデルで体外循環実験を行いました。この研究は、小型動物モデルで形を変えて今も続けられています。
ひとつの研究が次々と広がっていく


肝臓学にとっては暗黒の時代でした。
北村
-色々な研究をされてきたように見えていて、実はつながっているわけですね。肝線維化活性マーカーの研究もそうなのでしょうか。
松浦
そうです。私が医師になった1983年当時は、まだC型肝炎はみつかっていなくて、NonAとかNonBとか言われていたんです。ウイルスが見つかったのは1989年ですから、その間は基礎研究をやるしかありませんでした。肝臓学にとってまだまだ暗黒の時代でした。
それからC型肝炎やB型肝炎を抑える薬が作れるようになって、今はまた線維化に注目が戻ってきています。これは肝臓だけに限りません。腎臓でも心臓でも線維化に関することが注目されています。
北村
-長いスパンを経て、治らなかった病気が治るようになって、基礎研究をやってきてよかったというような、大きなやり甲斐を感じられたのではないでしょうか。
松浦
研究者として良い時期に巡り合ったと思います。ビタミンAについては生理的な面から病理的な面に目が向けられて、治療に結びついていきました。バイオ人工肝臓でも毒物に当たるものが同定できて、致死的なものを薬で抑えられる可能性が出てきました。
肝臓研究の世界に入ったのは、伊東細胞の強く光ってたちまち消退する蛍光が綺麗だなとおもったのがきっかけでした。その後肝臓病の分野は、C型肝炎ウイルスが見つかって、本当に薬が色々出てきて、臨床診断、治療法は長足の進歩を遂げています。


最初に楽しいなと思うことがやり甲斐にもつながりますし、研究においてはそういう想いが大事なんですね。
ビタミン濃度の基準範囲を設定したい


北村
-今回ブランディング事業ではどのような研究をされているのでしょうか。
松浦
疲労にはメンタル以外のファクターもいろいろあります。そのひとつとしてビタミンもあります。そこで都会のビジネスマンに、ビタミンDが足りているかどうかを評価しようと考えました。
去年の段階でテスト的に教職員のビタミンDを測定してみたら健常者でも濃度が低かったんです。ビタミンは日光にあたることで生成されますから、もしかしたら都会のビジネスマンは十分に陽に当たっていないのかも知れないとも考えられます。
また、ビタミンに関しては基準値が設定されていないという問題もあります。だから足りているかどうかの判断ができません。そこで今回健常者の人のビタミンDの濃度をたくさん測って、基準範囲を決めることをテーマにあげました。
北村
-基準となるものを設定するには、多くの測定データが必要になりますね。
松浦
研究室で手動で測っていると1万件といったデータは測定できませんし、測定結果もバラバラになります。そこで今回は臨床検査用の全自動高速液体クロマトグラフィー・質量分析システムを、附属病院の中央検査部に設置し、検査としてビタミンDを計ることにしました。この臨床検査用の装置は日本で初めてのもので、島津製作所との共同研究です。
物差しとしての基準範囲を決めることは地味ですが大変意義のあることです。それがあって初めて検査値から適切な判断ができるようになります。そういうことに取り組めるのはトランスレーショナルリサーチ研究者としての醍醐味だと思いますね。
対談者プロフィール

SI医学応用研究センター センター長
松浦知和(まつうら ともかず)
都立三田高校を卒業し、二浪して慈恵医大に入学。バスケットボール部では戦力にならず、ベンチワークに勤しむ。卒業後第一内科(現・消化器肝臓内科)とペンシルバニア医科大学(現・ドラクセル大学医学部)で肝臓星細胞とビタミンAについて研究。神奈川県立厚木病院(現・厚木市民病院)と柏病院で消化器内科医として修練を積む。2000年に臨床検査医学講座に移籍。2014年から同講座教授。現在、安定同位体医学応用研究センター長兼務。

北村晃(きたむら ひかる)
自律性を重んじる慈恵医大のフィロソフィーに惹かれ入学。三年半の座学を経て臨床現場にて実習をし、臨床の難しさと奥深さに触れる。患者さんのバックグラウンドを聴くことを得意とする。一年次より大手コーヒーチェーン店にてアルバイトをし、「教えることは教わること」をモットーに人材育成を担当。コーチング方法を模索する日々を過ごす。暇さえあればコーヒーを淹れている。