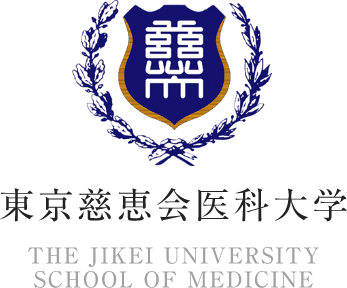第5回 明日の医療に役立つ研究に取り組んでほしい
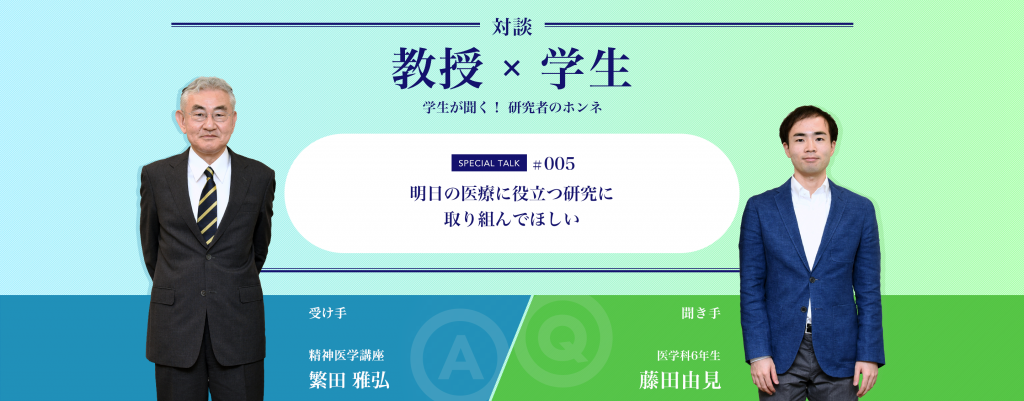


今回ご紹介するのは、アルツハイマー病などの認知症疾患を専門とする精神医学講座主任教授の繁田雅弘さんです。慈恵医大を一旦離れ、首都大学東京(現:東京都立大学。以下同じ)で学部長や副学長を歴任した後、再び慈恵医大に戻り、医療人材の育成や地域医療への貢献に取り組んでいます。
理屈を超えて惹かれるところがなければ研究は続けられない


藤田
-精神科の臨床研究医を目指したきっかけは何だったのでしょうか。
繁田
私は親族などの身近に医師がいなかったために、研究医について具体的なイメージは持っていませんでした。ただ、医師としては、まず現場で臨床を経験してから、その先があるとは感じていました。研究するにしても患者さんのことを肌で知っておくことが必要だと思ったのですね。今もそれが続いています。
精神科に進んだのは、教えたり、指導したりするより、患者さんの話を聴く方が好きだし、得意だと思っていたからです。精神科医の基本は患者さんの話を聴き続けることです。話を聴く中で患者さんに気づきや発見をしていただきます。それを得意と感じていた私が精神科医を選んだのは自然の成り行きでした。


藤田
-確かに先生と話していると安心感があります。影響を受けた先生はいらっしゃいますか。
繁田
一番は1966年に慈恵医大の教授になられた新福尚武先生ですね。新福先生の書かれた本は学外の研究者にも教科書として読まれているほど影響力のある方でした。
私が書いた論文をいつも新福先生にみていただいていたのですが、先生からは肩の力を抜いて、病気の本質を日常の言葉で表現することを学びました。そのためには本質を見抜く力が必要ですが、先生にはまさにそれがありました。
回診の時でも、偉そうに患者さんに説明するのではなく、ベッドの横から患者さんの辛さを丁寧に深く聴いていました。その患者さんの担当の医師だけではなく、誰もが先生の回診を見学したがったという伝説の人です。

私もそういう医師になることを目指してきました。


藤田
-精神医学の中でも老年精神医学、特にアルツハイマー病がご専門ですが、どうしてその分野を進まれたのでしょうか。
繁田
元々は医局の研究チームの一員として、超音波装置で頸動脈の血流を測定して分析するために、老人病院や老人ホームを訪問して認知症の人のデータを集めたりしたのがきっかけです。
最初は、言われてやっていただけでしたが、わかってくるともっと知りたくなるものです。例えば、アルツハイマー病でも血管性認知症でも頸動脈の血流は減ってきます。でも原因は全く違います。医局の先生はそれをデータで証明しようとしたりしていました。
データを集めるためには患者さんに理由を説明しなければなりませんし、結果が出たらそれをフィードバックしなければなりません。認知症の患者さんでも普通の言葉でわかりやすく説明すれば理解してもらえます。
実際にコミュニケーションしていると、患者さんの別の辛さもわかるようになってきて、もっと役に立ちたいと考えるようになりました。それがこの道に入ったきっかけです。

自然の流れだったわけですね。
繁田
ただ、そうは言っても面白くなければ選ばないでしょうね。直感的に惹かれないとそちらの道に進まないと思います。
研究にはクリエイトしなければならない部分があります。次に何をテーマにするのか、プログラムはどうするのか、どんな方法で研究するのか、と言った部分です。それを積み上げていくと結果的にすごい研究が生まれます。胸が高鳴るような気持ちがなければ続けられません。
認知症の人が生きがいを見出せる社会に


医学的な研究の重要性はどんなところですか
藤田
-医学的にみて先生の研究の重要性はどんなところにあるのでしょうか。
繁田
高齢化社会になって認知症の人は増えています。それを社会として荷物のように考えがちですが、その発想を変えたいと思っています。60歳であれば、まだ十分若々しいですし、認知症であっても判断力や技術力は持っています。そういう人が活躍できることが、国や社会の発展につながります。決して荷物なんかじゃないんですね。
認知症の人が増えているからこそ、その人たちに生きがいを持ってもらえるようにしたい。それが真に成熟した社会だと思いますし、幸せな人が増えていきます。私はそういうところに、やりがいを感じています。


認知症は「いかにコミュニケーションをとるか」がテーマに なってきています
藤田
-これまでの研究によってどういうことが解明されたのでしょうか。
繁田
以前、認知症患者には脳の代謝をよくする薬が処方されていました。この薬は覚醒度を上げるので、集中力や注意力が増して知的機能の検査成績が上がってきます。しかし、それは認知症の認知機能の低下を治すこととは違います。私は「脳代謝改善薬は認知機能障害の治療薬ではない」と主張しました。
最近では、いかにコミュニケーションをとるかがテーマになってきました。確かに、認知症が高度に進行した人は言葉を失ってしまいます。しかし、それでも話しかけ続けると片言の言葉を返してくれたり、表情が変わったりすることがあります。そのうちに「生きていく糧を見出してくれるのでは」と期待しています。
こういう研究はデータをとってAとかBとかを明らかにするものではありません。事例を積み重ねて「コミュニケーションに価値がある」と発信していくしかないのです。
藤田
その一つが、先生が取り組まれている「栄樹庵 SHIGETAハウス※」の活動ですね。
繁田
そうです。そこにつながっていますね。元々は母が一人で住んでいたのですが、加齢や孤独も影響して、生活上の失敗も増えてきました。改めて本人にどう暮らしたいかを聴くと「施設に入りたい」ということになり、実家が空き家になったんです。
その空き家に不審者が入り込むような事件もあって、どうしたものかといろいろな職種の方と話しているうちに「認知症の人が遊べる場にしませんか」という提案があって、昨年「栄樹庵 SHIGETAハウス 平塚カフェ」として活動をスタートさせました。栄樹庵とは、母が長年茶道を教えていた、自分の茶室の名前です。病院とは違う発見も多くあって、視野を広げる良い機会になっています。
ただ、運営は大変です。地域の様々な専門家の人たちが協力してくれて、カフェを運営するとともに、認知症の人を支援する人向けの勉強会や講演会を開催していますが、維持するための費用はかかります。勉強会を録画して有料のネット視聴番組にしたり「どう運営費を確保するか」を考えているところです。
※SHIGETAハウスは、繁田教授が中心となって立ち上げたSHIGETAハウスプロジェクトによる認知症支援の取り組み。
詳細はサイトをご覧ください。
> SHIGETAハウスプロジェクト


医学研究の本質を次の世代に伝えたい


藤田
-研究を通して世の中をどう変えていきたいと考えていますか。
繁田
認知症の患者さん本人の意向を医療に反映できるようにしていきたいですね。認知症の人が病院内で転倒して大腿骨を骨折したとしましょう。今はどんな手術をするかを家族と医師が話し合って決めてしまうことが殆どだと思います。ただ、医学が決める決断がその人の人生において必ずしも正しいわけではありません。本人の判断を尊重したいと思います。
確かに認知症の人はパッと答えることはできないかもしれません。しかし、思っている以上に多くのことを理解できます。今、それを証明しようとしています。そのことが伝われば、患者さんの意志を聴こうと努力するようになり、より本人の意向に寄り添った医療ができるようになります。10年後20年後にはそうなっていてほしいですね。
今はあくせく論文を書かなければならない立場ではありません。それよりも社会に良い影響を与える研究成果やメッセージを出していくことを意識しています。できるだけ病院の外の弁護士や税理士、文学者や社会学者といった人たちと交流するのも、医学の考え方を広めるためです。

社会の役に立つために医学があるということですね。


繁田
医学は実践科学です。発明は社会の役に立つ形になって初めて意味を持ちます。医学も同じです。重要なのは実装化です。
スウェーデンの大学に留学していた時のボスの口癖は「その研究は診断か治療の役に立つのですか」「すぐに役立つ研究をしなさい」でした。今自分が指導する立場になって、同じことを言っています。


藤田
-首都大学東京の副学長から慈恵医大の教授に転じられた背景にもそういう想いがあったのでしょうか。
繁田
自分が学んできたことを医師に伝えたいという想いから慈恵医大に戻ってきました。当時、首都大学東京で学長を務められていた原島文雄先生はロボット工学の権威ですが、良く「大学の一つの使命は知識の継承である」と仰っていました。自分は何を伝えられ得るのだろうか、と考えた時に「今まで学んできたことを慈恵医大の人たちにも伝えたい」と考えるようになったのです。
そんな時に医局から声をかけてもらったので、挑戦する気持ちで戻ってきました。就任時に同窓会の場で「流れを変えたい」と宣言しましたが、認知症の患者さんとコミュニケーションする姿を若い先生たちに見せることで、認知症でも前向きに臨めるということを次の世代に伝えたいと思っています。

今まで学んだことを次世代へ伝えたいと思っています。
藤田
ー慈恵医大は臨床研究がやりやすいと言われていますが、やはりそう感じられますか。
繁田
接することができる患者さんの数が多いという特徴に合った臨床研究はやりやすいですね。実装化を前提に、どういう治療の役に立つかという切り口でアプローチすれば大きな成果を得ることができます。人間としての患者さんに元気になってもらうための研究は建学の精神にも合致しています。
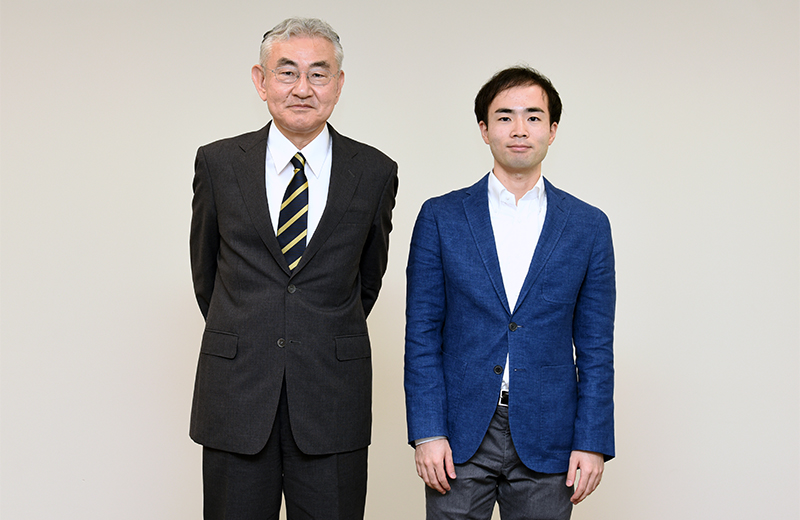
藤田
ーこれから研究者を目指す人にアドバイスをいただけますか。
繁田
論文の数を追うだけの研究者にならないでほしいですね。あくまでも医療は実践科学です。実装化と明日の医療に役立つ研究を意識すると、「これだけの人を救うことができた」「病気に対する偏見を変えられた」といった大きなやり甲斐を感じることができます。
医師の取り組む研究は自分のキャリアアップではなく、医学の発展のために行うものであってほしいです。この本質を見極めていれば、研究者として有意義な人生を送れるはずです。そういう志のある方は是非本学で研究に取り組んでください。
対談者プロフィール

繁田雅弘(しげた まさひろ)
東京慈恵会医科大学を卒業後、精神医学講座に所属し、1992年よりスウェーデン・カロリンスカ研究所老年病学教室の客員研究員、2003年より東京都立保健科学大学教授、2005年より首都大学東京健康福祉学部学部長、2011年より首都大学東京副学長を務めた。2017年より東京慈恵会医科大学精神医学講座教授に就任、同時に首都大学東京(現 都立大学)の名誉教授の称号を得た。

藤田由見(ふじた よしみ)
東京都立小石川中等教育学校を卒業後、二年間の浪人生活を経て慈恵医大に入学。臨床実習にて医学を学ぶ傍ら、解剖学講座にて研究活動に励む。陸上部では短距離を専門とし、Jikei CPR-study groupでは心肺蘇生法の普及に取り組む。インドアを好むが自然が好きで山岳部とダイビング部に所属。座右の銘は「人間万事塞翁が馬」。