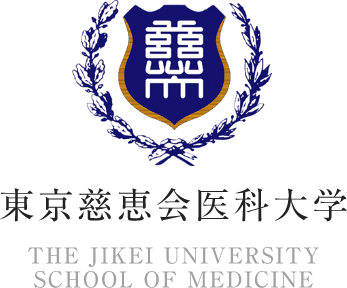第6回 臨床研究とは科学を究めることではなく、患者さんに貢献すること
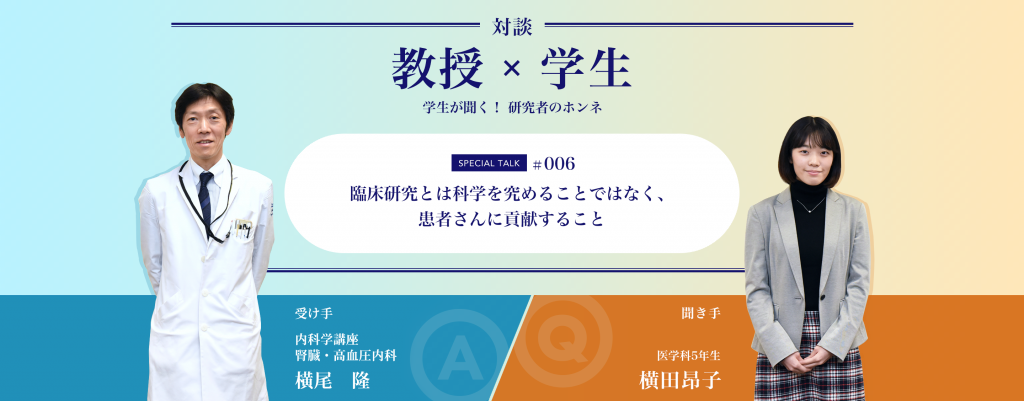


今回ご紹介するのは、幹細胞を利用した「腎臓再生」に挑戦し、20年以上かけて臨床への応用の可能性を切り拓いた腎臓・高血圧内科教授の横尾隆さんです。“神の領域”と言われた研究に挑戦し続けた背景にはどんな想いがあったのでしょうか。
目の前の患者さんを救うための研究を
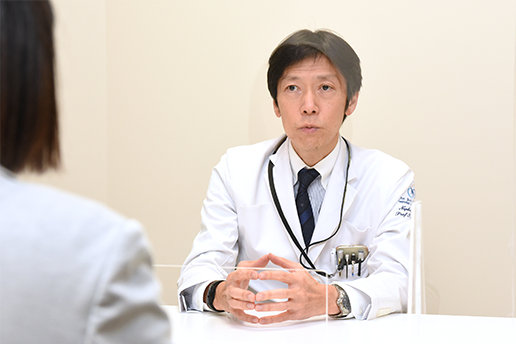
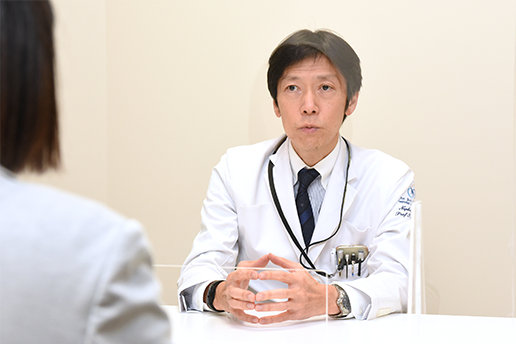
横田
-臨床研究医の道に進もうと考えたのはなぜなのでしょうか。
横尾
研修医の頃は特にこの分野ということはなく、漠然と内科系に進むんだろうなと考えていました。当時はゲノム医療が注目されていて、癌もゲノム改変によって治せると言われるようになり始めた時代です。
研修医の時に透析治療を受けている小学生の患者さんと接する機会がありました。透析治療を我慢して受け続けていたのですが、残念ながらお亡くなりになりました。その姿を目の当たりにして、この腎臓病を何とかしたいと考えたのです。
腎臓というのはすぐに死に直面する病気ではないだけに、それほど重く捉えられないことが多いのです。
しかし、患者さんは多くの制約の中で閉塞感に苛まれています。合併症が多く感染症にも弱い。最近の透析医療の進歩により患者さんのQOLは格段に上昇しましたが、それでも合併症が多く生命予後も健常者より短くじわじわと追い込まれていくのです。
こんな光の見えない状況から患者さんを救いたい。そう思って当時の慈恵医大の第二内科に入れてもらいました。

腎臓病に苦しむ患者さんの姿を目の当たりにして、何とかしたいと考えたのです。


横田
-その当時は腎臓再生医療は今ほど注目されていなかったと思うのですが、なぜその分野に注力しようと考えたのでしょうか。なにかきっかけがあったのでしょうか。
横尾
研究は情熱だけでは続けられません。注目度も重要です。注目されることで、サポートしてくれる人たちが現れ、資金も調達できます。研究を続けられる環境が必要です。その意味でも時代的な背景は重要なのです。
大学院生になって英国に留学していたのですが、その時は細胞が相手の基礎研究ばかりしていました。どうしても患者さんと距離があります。もともと患者さんの役に立ちたいと基礎研究に取り組んだはずが、なかなか患者さんに研究成果を届けることができなくて、焦りばかりが先立ちました。
帰国してみると、日本ではゲノム医療や遺伝子治療に大きな注目が集まっていました。そこには人も研究費もついてきます。腎臓病単独では注目度が低く研究を続けるのが難しい状況でしたが、腎臓病の遺伝子治療であれば研究を続けられると考えました。そこで本学の遺伝子治療研究部の研究員になりました。1997年のことです。
神がかりが重なって一気に加速した


横田
-1997年というと遺伝子治療の成功例が出始めた頃ですね。
横尾
当時、幹細胞移植が注目され始めていました。これを腎臓に応用できないかと幹細胞を用いた遺伝子治療に取り組みましたが、単一遺伝子疾患でない腎臓病ではなかなか成果につながりません。ただ、その研究が腎臓再生医療へとつながっていきました。
腎臓は壊れると元には戻せません。透析は代替医療であり治癒を目指すわけではありません。根本的に治療するためには、作り直すしかありません。この再生に遺伝子治療で用いていた幹細胞が使えるのではないかと考えたのです。
当時は再生医療という言葉さえも存在しませんでしたが、幹細胞が扱えるというのは私にとって大きなアドバンテージになりました。研究を続けていたら、腎臓領域で幹細胞を扱える日本でも珍しい研究者となっていました。それで風向きが変わりました。研究にスポットライトが当たるようになったのです。


横田
-スポットライトですか。
横尾
研究者にとってスポットライトが当たることは大事なことです。注目されれば資金がついて、多くの人がサポートしてくれます。私もそれで一気に研究が進みました。今考えると全てがラッキーだったとしか言いようがありません。
そのラッキーは続きました。幹細胞の一つに間葉系幹細胞という種類があって、それを用いてラットではうまくいったのですが、人に応用するところで大きな壁にぶつかりました。その時に京都大学の山中伸弥教授のiPS細胞が出てきたのです。
「あれっ、これってまさに僕のためのもの?」と思いましたね(笑)。それで一気に研究が花開いたんです。

運の力もあったのですね。
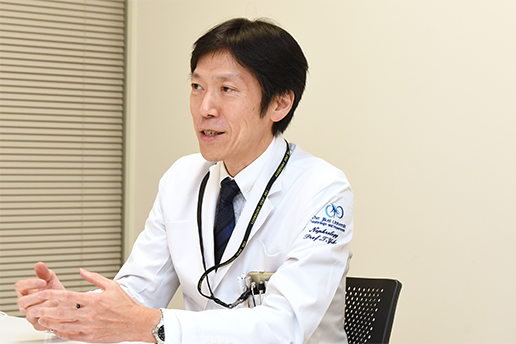
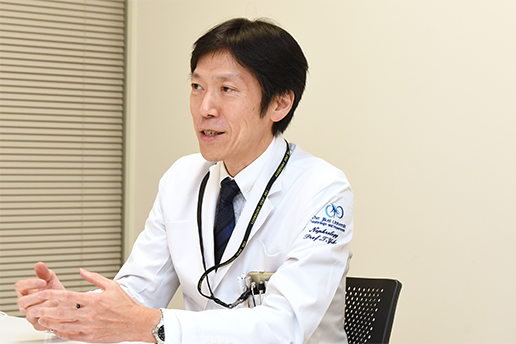
横尾
運も重要です。私は臨床医として患者さんを実際に診療することが中心となります。どうしても研究に割く時間の制約があります。しかもラットやマウスという小動物はできても、大きな動物を扱うノウハウはありません。そんな時にその分野のトップの研究者がほとんど手弁当で参加してくれました。
iPS細胞もそうですが、あり得ないタイミングであり得ないサポートが受けられました。腎臓で苦しむ患者さんを救いたいという強い信念に共感してくれたことは間違いありませんが、全てがラッキーとしか言いようがありません。
横田
ーなぜそういうラッキーが起きたのでしょうか。
横尾
私が腎臓の再生医療に取り組み始めた時には、周囲から「馬鹿なことを」と冷ややかな目で見られていました。iPS細胞であっても臓器を再生させるのは無理だと言われていました。特に腎臓は難しい臓器です。それを再生するのは“神の領域”と思われていました。
研究が一気に進みだした頃、自分が「神がかっている」と不思議に思ったこともありました。私自身の手で助けられず見送った多くの患者さんたちが、私を後押ししてくれているのではないかと考えたりもします。
「患者さんに再生した腎臓を届ける」という使命を遂行したいという強い気持ちがあるので、寝ずに研究しても平気ですし、普段の診療にも力が入ります。そういう自分を見守ってくれているのかも知れません。
再生医療は臨床応用の最終段階に
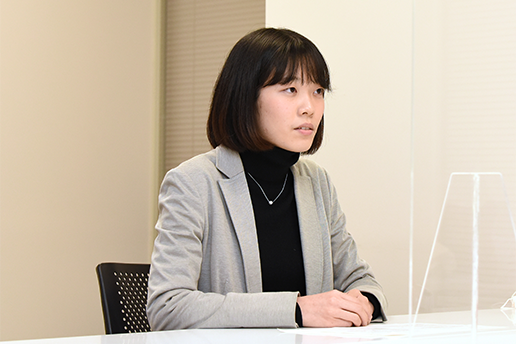
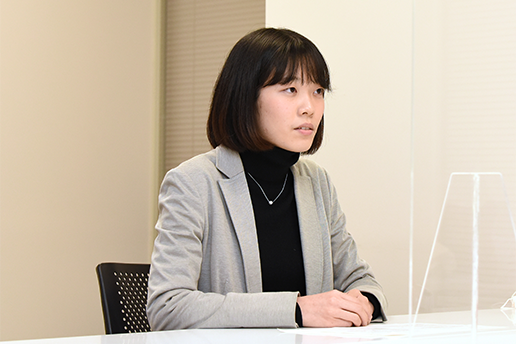
横田
-最先端の研究をしていて周囲からの期待も高まっていますが、プレッシャーはあるのでしょうか。
横尾
もともとキャラ的に目立ちたがり屋で、なんでも一等賞が好きなんです(笑)。それが原動力になっているという一面はあると思います。でもプレッシャーはいつも感じていますし、たまに押しつぶされそうになることもあります。
腎臓病の患者さんは辛い毎日を送っています。のどが渇いているのに水が飲めないという過酷な状況に置かれている人も多いのです。「生きているから良い」ではなく、好きなだけ水が飲めるようになって欲しい。それを実現するまで私は諦めません。

腎臓の再生医療の可能性が見えてきた今、国内外から期待しているという手紙や電話をいただきます。それに一日でも早く応えたい。それが大きなプレッシャーになっています。これまで少ない研究費しかなくても寄付をいただこうとしなかったのは、いただくことでプレッシャーがこれ以上大きくなることを恐れたからです。
腎臓の再生医療への期待は現場にいるとひしひしと感じます。透析を受けている患者さんはいわば暗いトンネルの中を歩いているような状態なのかもしれません。そこに光をもたらしたい。少しでも行く先に出口の光が見えれば足取りが軽くなるし頑張れるはずです。

今は信じて待ってもらうしかありません。


横田
-腎臓の再生医療の研究はいつごろ実を結ぶのでしょうか。
横尾
はっきりした時期はまだお答えできませんが、今は前臨床研究の最終段階に入っています。個人的にはここまで来れば本当にできるのではないかという確信を持っています。ただ実現に近づくとサポートする人たちも多くなり、その分、軽々にはものが言えなくなります。
最終段階に入るゴールが近づくほど、ゴールが遠くなっていくような感覚もあります。でも今日の一歩はゴールに向けた一歩であることは間違いありません。確実に一歩一歩前進していくしかないと思っています。
透析を受けている患者さんの中には、自分のためではなく、治療を進歩させるために積極的に治験に手を上げてくれる方もいます。患者さん同士やご家族の方たちの絆も強い。それだけ長く忍耐を強いられる病気なのです。また腎臓病をよく知らない方々からそれを理解してもらえない。その病気と戦っている患者さんから多くのことを勉強させてもらっています。
患者さんに優しいのが慈恵の特徴
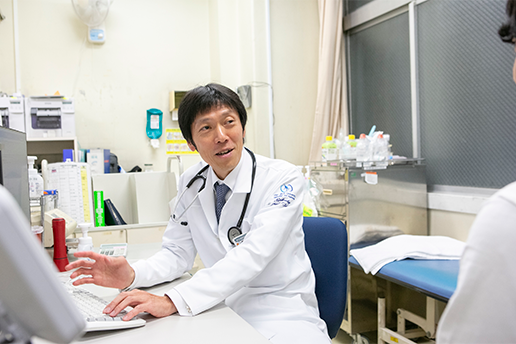
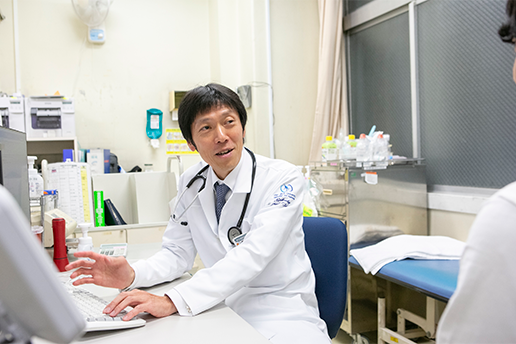
横田
-臨床と研究に並行して取り組むのは大変ではないのでしょうか。
横尾
体力的には大変ですが、臨床があるからこそ研究の進むべき道を誤ることもないと思っています。私が考える研究の最終ゴールは、科学を究めることではなく、患者さんに貢献することです。
ひたすら追究することですごい論文を書くことはできるでしょう。でも私は少しでも早く成果を患者さんに届けたい。データを補強している暇はないんです。臨床で常に患者さんを見ていることで、最短距離でゴールに向かうことができます。


横田
-それが慈恵らしさでもありますね。
横尾
洗練されていないと言われるかも知れませんが、そうだと思います。研究は山あり谷ありです。一筋縄では行きません。そんな時に臨床と研究の両方をやっていることで自分が突き動かされている気がしています。
横田
-慈恵の研究の特徴はどんなところにあると思いますか。
横尾
慈恵全体に言えることですが、とにかく患者さんに優しいことです。病院でもそうですし、それが研究者のモチベーションにもなっています。
建学の精神である「病気を診ずして 病人を診よ」という言葉に対して「病気を診なくてどうするんだ」という人がいます。それは大きな勘違いです。病気だけではなく、病気を持っているその人、そしてそのご家族や社会背景を含めた全体像を“診なさい”、という意味です。病気を治すのだけが医療ではありません。だれでも歳を取りいつかは亡くなるわけで、完全治癒を目指すだけでなく病気を共存しながらも幸福に暮らせることを目指す場合もあります。その患者さんにとって何が一番大切かを考えながら診療にあたるには“病気を診る”だけでなく“病人を診なければならない”のです。

横田
ー研究者を目指す人たちに何かアドバイスがありますか。
横尾
どんな高い壁に突き当たっても、本気で頑張っていると誰かが助けてくれます。別の所の道が見つかったり、上から神の手が伸びてきて引き上げてくれるかも知れません。大事なことは、パッションを持って継続することです。少しずつでも進んでいくと、道は開けてくるものです。
私の場合もそうでした。腎臓の再生医療への実現はもうすぐです。慈恵発の世界初の治療法としてそう遠くない将来患者さんに届けられると思います。不可能を可能に変えるのは、研究者の熱意と絶え間ない努力の継続なのです。
対談者プロフィール

腎臓・高血圧内科 教授
横尾隆(よこお たかし)
1991年本学卒業、University College London医科大学留学などを経て2013年より腎臓・高血圧内科主任教授に就く。日本腎臓学会理事、NPO法人日本腎臓病協会監事などを務める。日々のストレス解消はジョギングで月250キロ前後走る。フルマラソン の自己ベストは50歳時の3時間48分。年々衰えを感じつつ自己ベスト更新が目下の目標となっている。

横田昂子(よこた たかこ)
豊島岡女子学園高校卒業。臨床実習に励む傍ら、細胞生理学講座にて研究を行う。女子バレー部と学生委員会に所属し、3年次には医学科学生会長を務めた。コロナ禍以前は「ぬいぐるみ病院」の保育園訪問を通して保健教育を実地で学習するなど、課外活動にも積極的に取り組む。座右の銘は「初志貫徹」。食は至福の時間です。