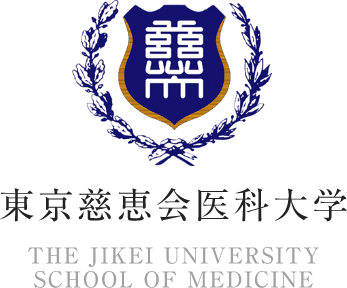第7回 素晴らしい人達との出会いを通して自分のやるべきことが見えてきた
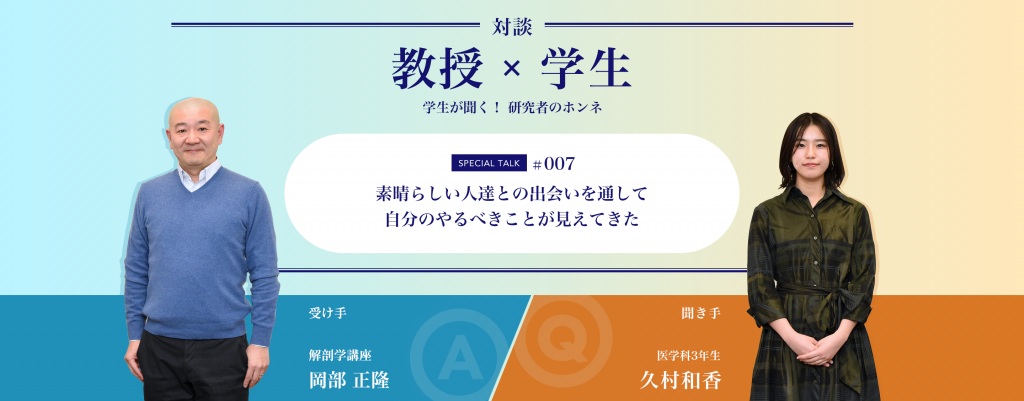


今回ご紹介するのは、解剖学講座教授の岡部正隆さんです。解剖学や発生学が専門で、魚やショウジョウバエの研究でも知られています。医師である岡部さんはなぜこうした研究分野に進んだのでしょうか。
自分にしかできないことを探した学生時代


久村
-なぜ医学部に進学されたのでしょうか。
岡部
もともと生き物が好きでした。高校では生物部の部長をやるくらい魚や昆虫が大好きで、将来は生物学科へ進学して生物学者になりたいと考えていました。
一方で医師という職業にも馴染みがありました。祖父も父も内科の開業医で、小さな頃は3世代で同居していたので、祖父の診療所で育ちました。医師の仕事を身近で見ていましたから、医師になるのは特別なことではなかったのです。
転機が訪れたのは高校3年生の時です。風呂場で父が「生物学者も良いけど、医師になれば人もみられるよ」とポツリと言ったのです。
この言葉が刺さりました。
今でこそ脳科学やゲノム科学の分野で生物学者もヒトを対象とした研究をしていますが、当時、ヒトを対象にした生物学的研究は医学部でしか行われていませんでした。
父の言葉から「人をヒトとして、ひとつの生き物として捉えると研究対象として面白いのでは」と考えるようになりました。高校3年生の11月でした。
慈恵での勉強は楽しかったですね。自分は勉強にムラがあって好き嫌いが激しい方でした。生物や化学が得意だったので基礎医学の勉強はとても楽しく、当時の医学科3年生以降の科目は好きなものばかりでした。医学部に入学してよかったといつも思っていました。


久村
-研究の道に進もうと考えられたのはなぜでしょうか。
岡部
部活でヨット部に入っていたのですが、土日にしか練習がなく平日の放課後は暇でした。解剖学や生理学、生化学とかいろいろな授業が始まり、実習で標本を観ながら、この細胞の中で何が起こっているのかさらに知りたいと思い、平日の夕方から学内の色々な研究室に顔を出していました。
発生学が好きだったので、最初は解剖学講座の福島統先生に習って実験をしていました。
そこでは研究成果を学会発表する機会までいただいたのですが、組織学的手法では調べつくされている感じもあり、その後は当時脚光を浴びていた分子生物学的手法を取り入れていた寄生虫学講座の片倉賢先生の研究室や細菌学講座の大野典也先生の研究室に通いました。
生き物を形作る発生のメカニズムを知るには分子生物学が必要だと思ったのです。
臨床実習に出て医師が臨床の現場で活躍しているシーンを見るようになると、臨床もいいな、と思うようになりました。中でも興味を持ったのは小児科でした。
先天異常の多くが遺伝子の問題なので、分子生物学を臨床医学の中に活かせるように感じました。
放射線科の画像診断にも興味を持ちました。当時の病理学講座には骨肉腫などの骨軟部腫瘍の病理診断の大家であった牛込新一郎先生がいて、日本中から難しい症例が慈恵に集まっていました。私が慈恵に入学する少し前に、世界で最初のMRIの商用機が慈恵に導入されたこともあり、こういった症例の先進的な画像診断学の研究を見て、他の大学にはないニッチな研究環境に身を置くのも良いなと考えたりしていました。
振り返ってみると、人がやっていないことに取り組むことで、自分自身が不二の存在になりたいと思っていたのかも知れません。
人と人との出会いから基礎医学の道へ


久村
-興味のある分野が多くあった中で、なぜ基礎医学を選ばれたのでしょうか。
岡部
6年生の夏休みに図書館で勉強をしていたら、小児科学講座の衛藤義勝先生が「基礎医学の研究をやりたいなら一流を見なきゃダメだ」とおっしゃって東京大学医科学研究所化学研究部の御子柴克彦先生を紹介してくれました。小児科に誘われるかと思ったのですが。
医科研を訪問した私は、御子柴先生の研究室を見て衝撃を受けました。当時は用いる研究手法によって講座や研究室が分かれているのが一般的でしたが、御子柴研究室では、組織学、生理学、生化学、分子生物学など様々な研究手法を用いて学際的に神経系の発生学研究に取り組んでいたのです。
「ここであれば何でもできる。ここで仕事がしたい」。一瞬でそう考えました。
御子柴先生の人柄にも魅了されました。初対面の私は、夕飯に誘われてロースカツ定食をご馳走になったあと、串カツをつまみに二人で日本酒を1升飲んだのに、その後、先生はスタスタと研究室に戻っていかれました。「こんなバイタリティーのある先生のもとで研究できたら面白そうだ」とも思いました。

「ここであれば何でもできる。ここで仕事がしたい」。一瞬でそう考えました


久村
-ショウジョウバエの研究をされていたと伺いましたが、
なぜショウジョウバエだったのでしょうか。
岡部
当時御子柴研究室の助手だった岡野栄之先生から「君はショウジョウバエをやりなさい」と突然言われたのです。発生異常を示すショウジョウバエの変異体から原因遺伝子を見つけることで、個体発生を支える遺伝子のメカニズムを明らかにしようというプロジェクトでした。
医師免許を取得して最初の仕事がハエか、とは思いましたが、もともと虫好きということもあり、これがやりだしたら面白い。遺伝学はすごく論理的で、論理的な思考のトレーニングになりました。
分子生物学の研究室は、大腸菌が増殖している間に寝る、それ以外は時間を惜しんで実験するという軍隊のような環境でしたね。
そんな中、岡崎にある基礎生物学研究所に半年くらい研究手法を学びにいくことになったのですが、そこで指導してくださった堀田凱樹研究室の千葉晶先生はちょっと違っていて、実験にあまり熱心ではないように見えました。
千葉先生は、実験をするよりもパソコンでイラストを描いている時間の方が長いくらい。実験している姿をほとんど見ませんでした。しかし、ある日、目の前で彼が導き出した実験結果は、その後論文となって科学雑誌「ネイチャー」に掲載されたのです。
大学院生だった私は「研究はガムシャラにやれば良いというものではない」と衝撃を受けました。それ以来、「科学は哲学。自分の個性を活かしたアート的な研究をやろう」と考えるようになりました。


久村
-ご自身の研究者としての強みはどんなところにあるとお考えですか。
岡部
生物系学部の学生は、様々な生命現象について研究しやすい生物を選んで学びますが、医学部の学生は、ヒトという生物だけを学ぶので、ヒトというシステムを四方八方から学ぶことになります。ヒトを例に、1種類の生物の生命のシステム全体を理解するための学びです。そう考えるとショウジョウバエを扱うにせよ、遺伝学の材料としてのショウジョウバエに留まらず、医学部で学んだ研究者はショウジョウバエに秘められている生命システム全体を観ようとする意識が高くなるのではないでしょうか。
ハエを眺めているだけで、いろんな疑問が湧いてくるんですよね。そんなところが評価されたのか、大学院を修了した翌年に、国立遺伝学研究所の広海健先生の研究室の助手に採用されて、合計で約9年半の間、ショウジョウバエを使って発生の研究をすることができました。広海先生は論理的に日常生活を送るとてもユニークな遺伝学者で、科学者としてあるべき姿を多く学ばせてもらいました。


岡部
いつかは自分の研究室を持ちたいという考えが芽生えてきた頃、ショウジョウバエの研究で研究室を持つのか、それとも少しは医師免許を役立たせる研究室を持つべきか考えはじめました。そこで、ロンドンのキングスカレッジに2年間留学する機会を利用して、ヒトと同じ脊椎動物を使った研究手法を学びました。
ゼブラフィッシュという魚とニワトリ胚を使った発生学研究を始めたのですが、そこで取り組んだのは、魚のような形をした祖先動物がどう進化して陸上の四つ足動物になったのかという謎解きです。祖先動物のゲノムに生じた突然変異が、発生のプログラムを徐々に変えて、からだの形を進化させていったのかを明らかにする、進化発生学という分野の研究です。
進化発生学は、ヒトのからだの形を理解する方法の一つでもあります。
その後縁あって、慈恵の学生のときに入り浸っていた解剖学講座に戻ってきました。今は皆さんに解剖学を教えています。
能動的に動くことができる医療人を育てたい


久村
-コロナをきっかけに、私たちの授業形態も大きく変化しました。岡部先生はカリキュラム委員長も担当されていますが、どのような取り組みをされているのでしょうか。
岡部
医学を学ぶ学生にとって必要な能力の一つに、自分で学ぶべきものを自分で探して学ぶ能力があります。情報化が進む中で医学や医療の情報が身の回りに溢れています。その大量の情報から必要なものを見極め、身につける能力が求められます。さらに、身につけた知識を現場で応用して使えなければ意味がありません。AIが医療の中で当たり前になる時代は目の前に来ています。その時代に求められる医療人を育てる必要があります。
慈恵では、かなり早い段階で、臨床実習を拡充したカリキュラムを開始しましたが、今は臨床実習以前のカリキュラムの改革を検討しているところです。
そこで起きたのが、新型コロナウイルスの感染拡大でした。高度なネットリテラシーを身につけるカリキュラムを考えていた矢先に、突然のネット漬けです。実は、講義のe-ラーニング化の可能性は以前から検討されてはいたのですが、感染拡大防止対策のために講義のe-ラーニング化が一気に進みました。結果として学生が必要な情報を必要な時に得られる、同じ講義を繰り返し受講できるといった学修環境が整いました。また、各教員がどのような講義をしているのかを教員間で確認しあうこともできるようになり、実習や演習など他の授業での学修内容を調整することが、各教員レベルで可能になったのです。


岡部
コロナ禍で重要になってきたのが、オンライン授業とオンサイト授業の見極めです。医師の養成には、臨床実習に限らず様々な能力を身につけるために、登校して行う実習が必要です。一方で、感染防止のためにも本当に登校してやらなければならない授業なのかどうか、全ての授業でその学修内容が吟味されました。結果として、カリキュラムがシェイプアップされ、オンラインとオンサイトのハイブリット型カリキュラムへと、この1年で教育スタイルは激変しました。
カリキュラム委員長の仕事はやりがいがあります。慈恵の教員はオンライン授業を行う上でも、学生のことを考えて手間を惜しまないこともよくわかりました。血の通ったハイブリッド型カリキュラムが実現できたのではないでしょうか。今年度の問題点を振り返って、来年度はもっと充実させたいと思います。

カリキュラム委員会の委員に学生がいることは慈恵の大きな特徴ですね。
岡部
学生目線でカリキュラムを毎年改善していくというルーティーンが確立できています。学生と教員が一緒になって次年度のカリキュラムを作っていくことで、学生が自ら主体的に学べる環境を整えていくわけですが、学生の能動的な学修スタイルを確立するためにも、学ぶ側の意見を反映させるのはとても重要で、学生と教員の双方にとって大きなメリットがあると思います。
私が担当している解剖学は、実習時間が長く実習回数も多く、一年を通じて学生の成長を見届ける授業でもあります。医学教育の真ん中に位置するこの科目を担当しているので、上級学生を担当する教員から成長した学生の印象を聞くと、カリキュラムの改善の効果を肌で感じられて楽しいですね。
多様性を受け入れるために医師ができることを


久村
-色々な役割をお持ちですが、2004年からNPO法人カラーユニバーサルデザイン機構の副理事長として、色覚バリアフリー・カラーユニバーサルデザインの普及啓蒙活動に取り組まれていますね。そこにはどんな想いがあるのでしょうか。
岡部
色の見え方、つまり色覚には多様性があって、色で分類された情報が正しく伝わらない人たちに対する配慮の必要性を、社会に啓発しています。多くを占めるのは医学的に先天色覚異常と呼ばれる人たちですが、私は色弱と呼んでいます。自分自身が強度の色弱なのですが、日常的にあまり不便は感じていませんでした。ただし、地図や路線図など色分けには識別できないものがあるので、周りの話についていけず苦労することはありました。


岡部
私の色覚では、赤と緑が似通って見えるだけでなく、赤が暗く見えるという特徴があります。学会で使われる赤いレーザーポインターの光が見えず、どこを指しているのかわからないため、わかっているようなフリをしていたこともあります。
そんな時にショウジョウバエの研究者仲間だった伊藤啓先生が同じ色弱であることを知り、一緒に色弱の人にも区別できる色の使い方を啓発する活動をはじめたのです。
男女40名に1名の割合でいる色弱は、病気ではありません。個性であり、感覚の多様性として捉えるべきです。こうしたマイノリティーを、社会がどう取り込み、そして多様性に対応するのかを考えなければなりません。身体の専門家である医師が果たす社会的役割は大きいのです。
最近まで小中高等学校では一斉に色覚検査をしていましたし、色弱だと医学部に入学できなかった時代もありました。マイノリティーを排除するという優生学的思想のもとでの社会対応を推し進めたのは、実は医師です。戦後から1996年まで存在した優生保護法という法律が最近問題視されていますが、私もこの法律によって生まれてこなかったかもしれないと考えると、ぞっとします。
医師や医師を志す人には「医師の社会的役割ってなんだろう」と常に考えてもらいたいですね。

マイノリティーを、社会がどう取り込み、多様性に対応するのかを考えなければなりません。
医師だからこそ個人的な要素にこだわってほしい


久村
-医師として未来を担う学生にアドバイスをいただけますか。
岡部
私には他人と競い合うという発想はあまりありません。
面白いと思ったことをやってきただけなのですが、振り返ると、人がやっていないニッチなところを選んできたようにも思います。
それが自分の個性なのかもしれません。失敗を恐れるがあまり、個性を前面に出せない人たちが増えているようにも感じますが、個性を活かしてもらいたいですね。
医師免許を持っていれば、食いっぱぐれのない人生を送ることができるかもしれません。でも医師免許は生き方を教えてはくれません。
職業の三要素は経済性、社会性、個人性と言われていますが、生計をたてる経済性要素と、社会貢献する社会性要素は、医師免許があれば満たされるでしょう。しかし3つ目の要素である個人性要素、つまり個性を活かして理想を実現する要素は、自分で見極めなければなりません。
個人性要素をどう活かすのか、もしくはどう探し出すのか、ここに時間と手間をかけて欲しい。それができないと、仕事は苦痛になり、パフォーマンスも十分に発揮できないかもしれません。
私は素晴らしい人々の近くで学ぶ機会に恵まれました。それぞれの良いところに触れるたびに、自分もそうなりたいと考えて、少しずつ取り入れながら、自分の個性とすり合わせて、今の自分があるように思います。今後もいろんな人との出会いの中で、刺激を受けていくでしょう。
そうした自分探しの場として、慈恵は恵まれています。慈恵では、大学医学部にありがちな縦割り組織の弊害もなく、異なる分野の教員間の交流が盛んで、その教員たちがしっかりと学生に対峙しています。今も昔も、学生にとって様々な刺激を受けられる自由な環境があります。いろいろな人と話すことで、自己実現のための方法を探してください。

対談者プロフィール

解剖学講座 教授
岡部正隆(おかべ まさたか)
1993年慈恵医大卒業。大学院に進学し、微生物学で博士号を取得。国立遺伝学研究所発生遺伝研究部門の助手、ロンドンのMRC発生神経生物学研究センターでの留学を経て、2007年から解剖学講座教授。学生時代はヨット部、現在はその部長。趣味はスキーと魚。魚は酒の肴としてだけでなく、釣ったり、飼育したり、研究したり。解剖学講座水族館の館長でもある。好きな言葉は“諸行無常”

久村和香(ひさむら わか)
東京都立日比谷高校卒業後、一浪を経て入学。
1年次のヨーロッパ文化の授業で演劇の魅力に取り憑かれ、慈恵で30年あまり活動停止となっていた演劇部を再開させる。
コロナ禍で休部中だが、これを機により良い部活のあり方を模索している。
他にはJikei CPR Study group、国際交流学生の会(SGIE) 、ジャズ研究会に所属。多様な学びの場が提供される慈恵の恵まれた環境の下、最近は多言語の習得や作品鑑賞をしながら、自分の個性を追求している。