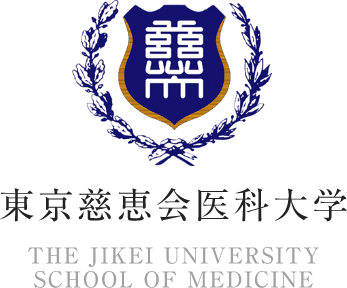第8回 辛いことの積み重ねでも無駄なことは何ひとつ無かった
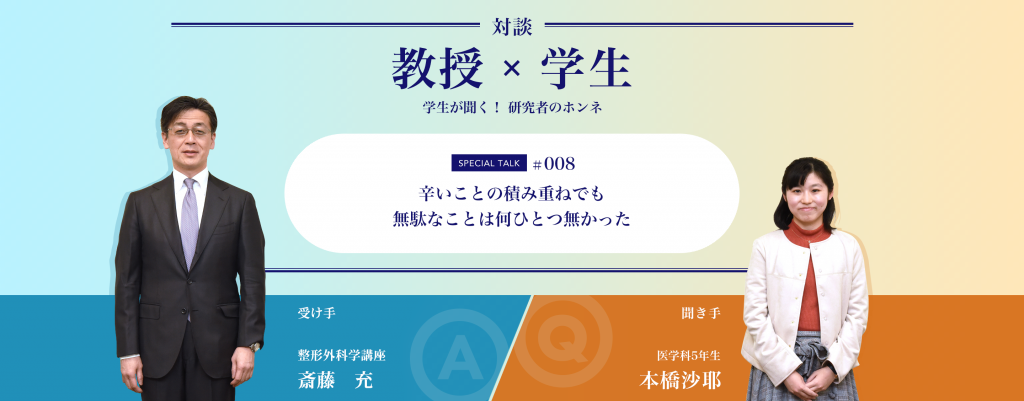


今回ご紹介するのは、人工関節の手術を数多く執刀するとともに、世界で初めて骨質を評価する方法を提唱した整形外科主任教授の斎藤充さんです。臨床と研究の両方の道をどのように両立させてきたのでしょうか。
サッカー選手だったことからスポーツ医学の道を志す


本橋
-なぜ整形外科医を目指したのでしょうか。
斎藤
祖父も父も歯科医だったので、それを引き継ぐつもりでいました。医師の道に進むことにしたのは高校一年の時です。
私は中学・高校とサッカーばかりをやっていました。一年で365日サッカーです。私はゴールキーパーでしたが、厳しい監督で毎日が地獄でした。でも中学3年生の時は東京都代表になって全国大会まで進み、東京都の最優秀選手に選ばれ、高校3年生の時には国民体育大会の東京都代表の副キャプテンに選ばれました。
監督の好きな言葉は「苦行を修行と思えば、道、自ら開ける」というものだったのですが、確かに「お天道様は見ていてくれている」と思える達成感がありました。「これ以上苦しいことはない。自分はどんなことでも耐えられる」と思えるようになっていました。
監督の存在は絶対です。その監督から突然「慈恵に行け」と言われたのです。私は「慈恵」の名前すら知りませんでしたが、慈恵には大畠襄先生というスポーツ医学の大家の先生がいて、日本で初めてプロスポーツ選手を専門に診療する部門が開設されていました。巨人軍のドクターもやっていたんです。サッカーで怪我をすることもあったりして、スポーツ医学も格好いいなと考えて、慈恵に進学することにしました。


本橋
-スポーツをしていたことで整形外科に進むことになったのですね。
斎藤
4年生から6年生の間は週替りで内科、外科など色々な先生のところで学び、それぞれの素晴らしさを感じました。しかし、自分のライフワークとして一貫して「整形外科でスポーツ医学をやろう」と当時は考えていました。スポーツ医学が最高の学問だと信じていたのです。
ところが入局してみると整形外科はスポーツ医学だけではないということを知りました。当時はまさに体育会系の講座ですごく厳しくて、朝6時に出て患者さんの体温を測って温度板に記入するなど診療の準備をして、そのまま夜遅くまで仕事をすることの繰り返しでした。
またまた地獄の毎日です。今の時代からは想像もできないような部活の延長のような日々でした。しかし、そうした日々患者さんと接することが、何かおかしいと感じるエビデンスの芽を見つけるためには重要なことだと後に気が付きました。今では先生や先輩に感謝しています。
分析という自分だけの武器が研究を継続するエンジンに


本橋
-臨床だけでなく研究もやっていこうと考えたのはなぜですか。
斎藤
大学院に行って基礎研究をしようと決めたのは自分でも驚きでしたね。スポーツ選手のケアをすることしか考えていなかったのですから。きっかけは、初期研修医の終盤である同期から「サッカーしてた時と違う。尊敬できるところが無くなった」と言われたことでした。
その同期は、大学でもずっとサッカーを続け東医体優勝、全医体3位と活躍する私を見て誇らしく思ってくれていたのですが、私が進もうとしている整形外科にサイエンスのイメージがなかったことで、そう思ったようです。確かに整形外科学講座は大学院に行かない講座でしたし、大学院に行こうとした時も周囲から反対されました。


斎藤
ただ、一方で自分が研究したいなら大学院に行くべきだと、背中を押してくれる上司にも恵まれ、何をしたいのかも無いまま、ただただ「これだけは負けない何かを身につけるため」取っつきやすく優しい研究者のいたDNA医学研究所(現・総合医科学研究センター)の分子細胞生物学部門、石岡憲昭先生のラボの門を叩きました。
石岡先生は脳の蛋白質の研究を専門とする理学博士のかたで、後に宇宙航空研究開発機構(JAXA)の教授になられました。
最初の1年間は、ただひたすらに脳の蛋白質の抽出と分析の手技を繰り返す日々が続きました。この繰り返しで蛋白質の操作一般の引き出しが増え自分で実験を立案し遂行できるようになっていました。


その後、整形外科の当時、准教授で第5代整形外科学講座の主任教授となられた藤井克之先生から1960年代にご自身が研究のライフワークとしていたコラーゲンの翻訳後修飾の研究をテーマとして与えられました。
しかし、コラーゲンの研究は既に世界で廃れていたことから、周囲の先生方から、「このテーマは災難に近いね、、、20年前の研究しろってね。可哀想に」とまで言われました。何しろ遺伝子解析や操作が全盛の時代に、蛋白質化学で更にコラーゲンって何と思われたのは当然でした。
しかし、私は与えられたテーマを貫徹するために大学院1年目で修得した蛋白質化学の手法を駆使して、世界で初めてコラーゲンの未熟、成熟、老化度を一つのシステムで分析する装置を確立することに成功しました。
と言うと簡単にと思えるかもしれませんが、この系の確立までには地獄のような作業の繰り返しでした。しかしこれも中高サッカー部時代の地獄に比べれば楽なものでした。無駄だ無駄だと当時は思っていた日々の実験の数々、そして膨大なデータの蓄積は、その後の私の研究人生の宝として助けてくれる武器となりました。「面白くない研究をやらされていたら、それはチャンスです」と今は言えます。

独自に開発した分析方法は国際ジャーナルに発表しました。私の研究の武器はこの分析系だけでした。
大学院を卒業して研究に邁進するのか、研究は終了して外科医として進むべきか悩みました。私は患者さんを診ているからこそ気が付く、何かおかしいという疑問を研究で解明する外科医になろうと決心をしました。それもコラーゲン分析で。このコラーゲンを分析できるのは自分だけでしたし、この武器で見返したいという思いもありました。
「何かおかしい」という感覚は新しい発見のきっかけになる


本橋
-コラーゲンはどう重要なのでしょうか。
斎藤
骨粗鬆症はカルシウム不足で起きると言われていましたが、患者さんを日々診ていると、骨密度が正常値でも骨折する患者さんが後を絶たないことに気が付きました。このことから骨の強さは骨密度=カルシウムのみでは説明できないのでは?と何かおかしいと思いました。そこで骨を調べてみると骨の体積の半分はコラーゲンで出来ていることが分かりました。骨は鉄筋コンクリートに例えることができます。コンクリートがカルシウム、鉄筋が棒状の蛋白質であるコラーゲン分子です。世界の誰も骨のコラーゲン、鉄筋の良し悪しが骨折に関係するとは考えてもいませんでした。コラーゲンの老朽化は建物すなわち骨の耐震強度を低下させるのではと考えたのです。


本橋
-カルシウムだけではないのではという発想はどこから出てきたのでしょうか。
斎藤
患者さんを診察していて「何かおかしい」と感じたからです。その感覚を見過ごすことができなかったのです。そこでヒトの骨コラーゲンの成熟度や老化度を独自に開発した分析装置で解析しました。まさにビンゴでした。骨粗鬆症で骨折している方の骨を分析すると過度に老化しているコラーゲンで満たされていることを発見しました。分析データが装置の画面に出てきたときの感動は今でも忘れることができません。世界の誰も知らないことが、今目の前にデータとして出ているのですから。
さらに動物実験も多数行い、コラーゲンを過剰に老化させてしまう原因も突き止めることができました。糖尿病や慢性腎臓病といった血管老化が進む生活習慣病では骨密度が正常でも骨折することが報告されていました。それらの骨を分析し、動物実験も行った結果、活性酸素の増大が骨のコラーゲンの異常をもたらす原因であることを初めてつきとめました。

それが世界で初めての骨質を評価する手法につながったのですね。


斎藤
オンリーワンの分析技術は持ち合わせていたので、骨折をおこすような病態やその病態の動物モデルの組織をこれでもかこれでもかと分析していました。自然とデータの引き出しが増え、患者さんとの接点が次の点と繋がり、臨床との接点として世界と渡り合えるようになりました。当時は学会発表だけで満足していました。
しかし、学会発表だけでは何のエビデンスにもならないことを思い知らされました。国際ジャーナルに掲載されてこそエビデンスとして認められ、追試をうけ普遍性があれば患者さんの診療に還元されることに気が付きました。
海外留学経験もありませんでしたので、英語は苦手でしたが、多くの論文を読み「論文英語」なるパターンがあることに気が付き、国際ジャーナルへの投稿が苦ではなくなりました。
私の研究は、3大誌といわれるnature、cell、scineceなどはありませんが、アクセプトされた20程の英文研究は、それぞれが海外の研究者から1論文あたり300〜780もの引用を受け追試され妥当性が検証されました。その成果はアジア人発の国際受賞を2期連続受賞するに至りました。
受賞はエビデンスのカケラにもなりませんが、妥当性、普遍性が世界で認められたことで、診療ガイドラインの作成委員となり、自分の研究成果が世界の患者さんの診療へと還元されるに至りました。


斎藤
「面白くもない研究」と自分も世界も思っていた研究でした。
しかし、患者と日々接することで感じる「何かおかしい」という感覚を払拭することができず、ただひたすらに動物実験、手術検体の分析、そして疫学研究へと展開、そしてそれを全て国際ジャーナルに投稿してきたことが世界の多くの臨床家、研究者から共感され「わたしもおかしいと思っていました(追試)」という大きな波になったと思います。
そして、世界の大御所であるProf Dr Ego Seemanから「Mitsuru、世界のフィールドに入るシューズとユニフォームはそろった、さあスタジアムに入ってこい、 well done」とメールが来たときの感動は今でも忘れることはできません。有名な研究室への留学経験がなくても、そして学内の小さな研究室で面白くない研究をやらされていたとしても、ただひたむきに患者と向き合い研究を継続することが大切なことだと気が付いたのは40歳になってからでした。
研究者にとって重要なのは論文とプレゼンと海外での発表


本橋
-研究者として成功する秘訣はどこにあると思われますか。
斎藤
研究を始めた当初は、私の研究がここまで世界で注目されるとは思っていませんでした。しかし、誰よりも多くの組織を診て分析し、同時に患者さんと接してきた自負がありました。そこから得られた膨大なデータと知識の引き出しは誰にも負けないと自負していました。学会や国際シンポジウムで発表するときでも質問に答えられなかったことはありません。その質問の全てのデータを自分のプレセンスライドキットの後半に隠しておいて、質問されている途中で、その答えとなるオリジナルデータを投影するのです。
コテンパンにしてやると意気込んで質問にたったドクターは、こりゃかなわんと成るわけです。無駄と思っていた膨大なデータの数々が自分を救ってくれる武器となりました。
また、研究者にとって重要なのは国際ジャーナルに論文を掲載することとプレゼンテーション能力に磨きをかけることです。和文は何のエビデンスにもなりません。学会発表も、どんなに素晴らしい受賞をしてもエビデンスのカケラにもならないのです。私も国内外で18の受賞をしていますが、それは嬉しいことですが国際ジャーナルに掲載しなければ5年もすれば忘れさられますし、何より世界の患者さんを救う研究になりません。

当初は、私の研究がここまで世界で注目されるとは思っていませんでした。


斎藤
海外留学の経験のない私のようなものでも、海外で発表することは度胸をつけるためには重要です。海外の人は英語が流暢かより、純粋に行っている研究内容を評価してくれます。
会話で私が得意としているのは“パードン攻撃”です。英語の意味がわからない時に「Pardon」と聞き返し、2度同じ事をいってもらうと8割程度、質問内容が理解できます。知識の引き出しは膨大にありますので、「ヒアリング」さえ乗り越えれば、英語論文のような堅苦しい英語ですが、堰を切ったように答えをかえすことができます。これで海外の学会も怖くなくなりました。
自分はセミの一生のような研究人生を送ってきました。有名な研究室に留学した経験もありません。そしてその時代、もてはやされた流行の研究にタッチすることさえできませんでした。しかし、日々患者さんと接することでしか得られない「何かおかしい」という感覚を大切にし、これでもか!これでもか!とオンリーワンの研究を継続することで世界と渡り合える日がくるんだなと、今は振り返ることができます。そういう研究者がいることは知ってほしいですね。「面白くない研究はチャンスだ」と前向きに捉えてください。
研究と臨床を両立することで突破口が見えてくることがある


本橋
-骨質の研究によって10年後、20年後はどう変わっていくとお考えでしょうか。
斎藤
コラーゲンの成熟、老化の分析にかけてはいまでも世界をリードしています。このオンリーワンの技術を最大限利用して、人生100年時代といわれる現代において老化の機序を解明し、新しい診断法から老化の予防、治療法を開発したいと思っています。身体は一つの水槽のようなものです。その水槽に血管も骨も軟骨も全ての臓器が浸っています。水槽の水が腐れば、すべてが一様に劣化します。
整形外科だから骨だけ診る、内科だから専門の臓器だけ診る、といった研究をする時代は終わりです。身体全体を見渡し診療にあたり、何かおかしいことがないかアンテナを巡らし研究に展開する、こうした意識を持ち続けることこそが今後10年、20年後に「研究で患者さんを救う新しい光」へと繋がる道であると思っています。


本橋
-研究者と臨床医を両立させることは大変ではないでしょうか。
斎藤
臨床は目の前にいる患者さんを診て治療して、その方の人生を晴れやかにすることができる素晴らしい医療です。
そしてその臨床を日々大切にすることで患者さんは新しいエビデンスの芽をさずけてくれます。そのエビデンスの芽を研究で解明するためには、少ない時間でも成果をだせる研究手法の確立と研究体制を整える必要があります。
確かに大学院を卒業した当初は研究と臨床を両立するペースがつかめなくて苦労しました。研究が進まなくなって、論文が出せなくなったのです。そこで1年間の中で実験に打ち込む期間と実験を止めて論文を書く期間をわけました。そうしたらどんどん論文が出せるようになったのです。

慈恵は研究と臨床を両立しやすい大学なのでしょうか?


本橋
-慈恵は研究と臨床を両立しやすい大学なのでしょうか。慈恵を目指す人にアドバイスもお願いします。
斎藤
臨床の疑問を基礎研究で解明する臨床医を育むのは学祖の教えにも繋がるものであり、そうした空気が大学の臨床および基礎講座に脈々と流れていると思います。臨床と研究を両立しやすい環境があると思いますね。ただ、慈恵には私のようなセミの人生のようなタイプもいれば、華やかなスーパースター研究者もたくさんいらっしゃいます。
臨床と研究の両立への取り組み方も様々です。色々な人を見て自分の道を探し出してもらいたいですね。
臨床が忙しくなると研究はもういいやと辞めたくなるときが必ず訪れます。しかし、一度研究の思考、手技をストップさせてしまうと、それを復活させるのは大変です。少ない時間でも継続できる研究手法を開発しオンリーワンの研究を続けていくことが大切です。
臨床をやっていると「この何かおかしいは、自分のもっている研究技術で解明できる」とピンと電気がはしることがあります。このゾクゾク感は研究をしていたドクターにしか見えない景色です。この景色を東京慈恵会医科大学の若手にも見てもらいたいと思っています。
この感覚を伝えていきたいですね。

対談者プロフィール

整形外科 主任教授
斎藤充(さいとう みつる)
1992年本学卒業後研究、臨床とも一貫して慈恵医大で研鑽を積んだ。2020年4月より整形外科学講座の第7代主任教授に就く。
厚労省の専門委員を長年つとめる。
また研究のみならず人工関節の手術数では大学病院勤務医中1位であり、担当患者さんに寄り添う早朝診察をおこたらない。
「患者さんが教えてくれる疑問を研究で解明して、世界の患者さんを救う」を合い言葉に、若手教育にも情熱を注いでいる。

本橋沙耶(もとはし さや)
桜蔭高校卒業。3年次の研究室配属で研究の楽しさを知り、以後、臨床実習の傍ら生化学講座で研究を重ねる。将来は臨床と研究の両立を目指す。
音楽部とESSに所属し、音楽部では団長を務めた。
医療系大学のインカレオーケストラにも参加し、広報担当も務めるなど、学外にも世界を広げる。座右の銘は「一期一会」。