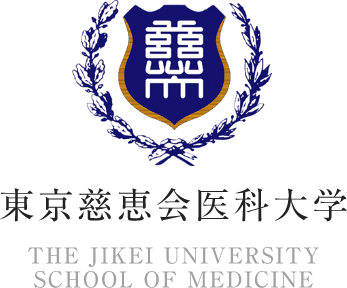「病気を診ずして病人を診よ」──変わらぬ理念と変わりゆく時代
東京慈恵会医科大学は、1881年に創設された成医会講習所を母体とし、140年以上にわたり、日本の医学・医療の発展に貢献してきました。本学の建学の精神である「病気を診ずして病人を診よ」は、創設者・高木兼寛が掲げた理念であり、現代においてもなお、すべての医学教育・診療・研究の根幹をなすものです。これは単なる標語ではなく、患者一人ひとりの背景や思いに寄り添い、全人的に向き合う医師を育てるという、私たちの使命そのものです。
現代の医療は、かつてないスピードで進化を続けています。AIやゲノム医療、再生医療といった技術革新に加え、超高齢社会や感染症の世界的流行、多様化する社会的背景など、医師に求められる資質や能力は年々複雑化しています。そうした中でも変わらないのは、「人を診る」視点を持った医師が、社会から強く求められているという事実です。私たちは、こうした社会的要請に応えうる人間性と専門性を兼ね備えた医師の育成に、真摯に取り組んでいます。
-798x1024.jpg)
主体的に学び、共に育つ──慈恵医大ならではの教育環境
本学の医学科では、6年間の教育課程を通じて、医学的知識と臨床技術、そして医師としての倫理観と人間性を段階的かつ体系的に養成しています。低学年では、リベラルアーツ教育や医療倫理、コミュニケーション能力の育成を重視し、「医師になるとはどういうことか」を自らに問いかける土台を築きます。中・高学年に進むにつれ、基礎医学、臨床医学を統合的に学びながら、実際の医療現場での実習を経験し、医療チームの一員としての自覚と責任を育みます。
2023年度からは新カリキュラムが本格稼働し、早期臨床体験を介したアクティブ・ラーニング、PBL(Problem-Based Learning)、シミュレーション教育など、主体的に学ぶ姿勢を育てる教育手法を導入しています。また、早期からの臨床体験、基礎・臨床研究への参加、英語での医学教育、国際交流プログラムの強化など、学生の多様な志向に応える環境が整備されつつあります。知識を一方的に受け取るのではなく、自ら問い、考え、行動する力こそ、未来の医療人に必要不可欠な資質です。
本学の教育を支えるのは、臨床・研究・教育のいずれにおいても経験豊富で熱意ある教員陣です。学生一人ひとりの学びに真摯に向き合い、きめ細やかな指導と支援を行うことを本学の伝統として大切にしています。加えて、学生同士の絆の深さも慈恵医大ならではの魅力です。学年やクラブ活動などを通じて、互いに高め合い支え合う人間関係が築かれ、それは医師としての将来においても大きな財産となるでしょう。
一生をかけて学び続ける──医師としての未来に向けて
卒業後の進路は多様化しています。臨床医として地域医療に貢献する道、大学院へ進学し研究者を志す道、行政や国際医療の分野で活躍する道など、学生の志は年々広がっています。本学では、こうした多様な将来像に対応すべく、キャリア支援体制の充実にも力を入れています。全人的に成長できる6年間を通じて、自らの進むべき医師像を見出し、それを実現するための力を養ってほしいと願っています。
「慈恵医大で学ぶ」ということは、単に医師免許を取得するための通過点ではありません。それは、医師として、人として、一生をかけて学び続ける覚悟を育てる時間です。本学には、皆さんがその第一歩を踏み出すにふさわしい環境と人材がそろっています。
これから医師を志す皆さんが、慈恵の地で「病気を診ずして病人を診る」医療の本質に触れ、確かな力と深い人間性を身につけ、社会に貢献する医師として羽ばたいていくことを心より願っております。